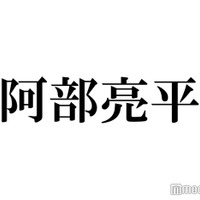さんきゅう倉田です。芸人をしながら、東大に通っています。
簡単に経歴を書くと、神奈川県横浜市にある小学校を卒業し、地元の公立中学校に進学し、推薦(成績は5段階でオール4という、とても地味な成績でした)で日本大学藤沢高等学校に進み、内部進学で日本大学理工学部建築学科へ。
卒業して東京国税局に入り、内部事務や法人の税務調査をしてNSC東京に入りました。芸歴16年目になります。
▶MARCHは今や高学歴ではない!?
さんきゅう倉田のGMARCH研究
ぼくが18歳の頃、つまり22年前は、GMARCHは MARCHだった。クラスメイトはみんな日大に行くから、MARCHを受験する人なんていなかったし、小学校や中学校の同級生がMARCHに行って、地元の駅で会って、どうだすごいだろ、なんて言われてもあまり分からなかった。
しかし、テレビのバラエティ番組を見ていると、MARCH出身の芸能人は「高学歴」として扱われている。
一方で、日東駒専出身の場合、学歴が紹介されることはないから、この上あたりが「高学歴」の基準だと認識していた。
確かにそうなのかもしれない。
ぼくが生まれた1984年は出生数が149万人で大学志願率は47%、志願者数は70万人。一方でぼくの東大の同級生が生まれた2004年は111万人で61%で志願者数は67万人。
志願者数が減っている一方で、MARCHの定員は増えている。
1984年 2003年 2024年
立教2,200人 2,900人 4,900人
青山2,200人 3,100人 4,900人
法政3,600人 5,000人 7,000人
中央4,300人 5,100人 6,600人
明治4,800人 5,500人 8,200人
※2024年は学部生の数を4で除して算出
◀MARCHは今、親世代より入りやすい
MARCHの定員数が大きく増加しているため、親世代と比べると格段に入りやすくなっている。
このような傾向は、学生の能力にも大きく現れているのではないだろうか。
MARCHにいま通っている学生とMARCH卒の年配者の論理的思考力にはかなりの差があるかもしれない。
親世代がMARCHを難関大学として捉えるような誤った認識を持つと、子供の受験に負の影響があるかもしれない。
例えば、大学受験に備えて、中学受験でMARCHの附属を受験することがあるだろう。そこに合格する児童は、同世代の中でも相当に賢い。地元の公立中学に進んでも、大学受験では早慶に受かるポテンシャルを持つ。
しかし、附属校に通うことであぐらをかいてしまう。勉強を頑張らなくともMARCHに行けるのだ。親もMARCHに古のイメージを持ち、それで満足してしまう。
中学受験には、大学受験への思い込みや過去のデータを刷新して臨む必要があるだろう。
▶いまどき浪人は少数派!
浪人は少数派、多数が現役合格が令和のリアル
1990年の現役進学率は51%だったが、現在は93%が現役だ。浪人することは当たり前ではない。
東大でも6割以上が現役だし、最も難関である理科三類では7割以上が現役である(他の科類より難易度が高いのに浪人割合が下がるのには、さまざまな理由がある)。
1960年の早稲田の政治経済学部の現役率は30%だったが、2024年は71.5%である。
現役率の増加は、出生数の低下と大学の定員増加だけが理由ではない。
推薦型選抜や総合型選抜の増加によって半分以上の受験生が一般受験をおこなわないこと、女子の大学進学率の増加が理由だ。
なお男子に比べ、女子は浪人を志向しない。これについては『なぜ地方女子は東大を目指さないのか 』(光文社新書)に詳しいので推奨する(とても良い本です)。
▶女子の大学進学率増加で起こった悲劇
女子の大学進学率増加で変わったこととは
地方では、いまでも「どうして女の子なのに大学に行くの?」と本人に聞いてくる年配者がいると聞く。
以前書いたが、神奈川に住むぼくの同級生も「息子には大学行ってほしいけど、娘には行かないでほしい。お金がかかるから」と言っていた(このとき、なんと答えればよかったか今でも考えている)。
このような実情は残るものの、女子の大学進学率は増加している。しかし、女子大を志望する受験生は減っているようだ。
その分、MARCHや早慶など共学の受験者が増えている。そうするとどういうことが起こるだろうか。
女子大の偏差値が大きく下がってしまった。
これもまた、親世代の女子大への認識が誤っていると、子供が自分と合わない大学に入ってしまうかもしれない。偏差値は靴のサイズなので、自分と合わないサイズでは、心地が悪いし、前に進みづらい。
子供の能力と大学の客観的なデータを正しく認識して、志望校を提案するとよい。
【こちらも読まれています】▶『「小学生の子供がいます。勉強させるより、遊ばせた方がいいでしょうか」に対する答えは…』