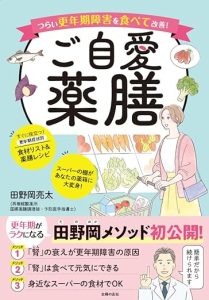こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
霜降(そうこう)の頃には冷えと乾燥に備え、肺をケア

2025年の霜降は10月23日から11月6日まで。秋が深まって冷え込みがぐっと増す頃、北国や山里では朝夕の露、白露が白い霜に変わります。紅葉が最盛期を迎え、木に残された完熟の柿の木には鳥が集まり秋の恵みを享受します。人にも生き物にとっても穏やかで幸せな季節です。
写真はここ熊本の、再春館製薬所ヒルトップまでの通勤ルートで見つけたコスモスです。秋から冬への移り変わりの土用の頃は、おなかを整えながら冷え・乾燥に備えましょう。
さて、秋の入り口の立秋の頃からここまでの間、中医学理論が“肺の機能”と捉えている「肺」「大腸」「皮膚」を中心とする臓腑とその働き、肺と腎の共同作業の「呼吸」をつかさどるので「辛み」という味がその働きを助けることなどのお話をしてきました。このような話のまとめにはなりますが、秋土用真っ只中なので、今回は「今が旬の食材」でおなか(=脾の機能)を整えながら冷え乾燥に備えて肺の機能をケアする方法についてお話しさせていただきます。
スーパーで遭遇した“旬だから安い”という食材を使って料理をしながら、薬膳・中医学の理論を当てはめながら紐解くと、「理にかなっているな…」と改めて思うことが多くあります。そんなことを思いながら作ったレシピとともに紹介させていただきます。
たとえば、1年中見かける水菜はこれからが旬。どんな働きがあるかというと…
まずスーパーの青果棚で目にしたのが「水菜」です。水菜は身体に摂り込まれたらどんな働きをするのか…がこちらになります。
■水菜
【辛/肺】辛みで“毛穴”を調節して“肺”をサポート!
【利水、通便、化痰】飲食物をスムーズに流して、肺のコンディションを整える。
【補肺】肺気を補って、肺のコンディションを整える。
水菜は1年中スーパーの青果棚に並んでいますが、最盛期は11月からスタートと言われます。熊本ではぐんと安くなったので、「そうか!旬になったんだ!」と気づきました。水菜は乾燥に強くはないので、保存環境に気を遣わないと1日でふにゃっとしやすいですが、「辛み」という性質があるので「発散」しやすいと捉えると、「なるほど、理にかなっている!」と思ったりもします。
さらに、上に列挙した水菜の効能を簡単に記載すると、「空気が冷たくなってギュッと閉まった毛穴を辛みで少し開いて皮膚のコンディションを整えて、飲食物の流れをスムーズにすることで大腸の流れを良くする。飲食物が大腸から出るまでをサポートするので、身体の下方への流れが整って肺の働きが行いやすくなる。」というところでしょうか。“旬の食材”として水菜をクローズアップしましたが、このように紐解くと「旬の食材はやっぱりその季節に摂ると良い。なるほど、理にかなっている!」と感じます。
驚くほどにすべてが理にかなっている…「水菜、蓮根、桃の白和え」
さて、水菜の他に“肺・脾の機能にうれしい食材”でおススメなのは、蓮根、豆腐、桃、えごま、生姜、かじきまぐろ、栗、マイタケ、シソ、水あめなどが挙がります。

これらの“肺・脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「水菜&蓮根&桃の白和え」です。涼燥&土用の“霜降”の時季におススメの水菜に、蓮根と桃の缶詰を合せてレシピにしてみました。
作り方は、水菜は洗って3cm幅に切ります。皮をむいた蓮根を鍋に入れ、蓮根がかぶるくらいのお湯にりんご酢(大さじ1)を加えて4~5分ほど茹で、厚み5mm程度の薄切りにします。桃(白桃缶詰:1/2玉2個)は5mm厚程度の薄切りにします。ボウルに水菜・蓮根・桃・水切りをした豆腐(小1丁)・鶏ガラ粉末(小さじ2)・えごま油(3g)・すりおろし生姜(小さじ1)・白みそ(小さじ1)を入れて混ぜ合わせて、器に盛りつけて、えごま粉末(小さじ1)をかけたら出来上がりです。
水菜と合せた蓮根は「胃のコンディションを整えて食欲を促す」働きが、豆腐は「身体に潤いを補って、おなかのコンディションを整える」働きが期待できます。水菜・蓮根・豆腐を合せることで「消化の働きをする脾の機能」と「乾燥が得意ではない肺の機能」に働きかける組合せになります。ここに合わせた桃・生姜はそれぞれ「潤いを補って肺の機能を助ける」「体表の毛穴を開き、肺を温めて機能を助ける」働きが期待でき、どちらも温性の食材なので涼燥の時季を迎えた肺の機能に喜んで欲しいと思って作ったレシピです。
水菜のシャキシャキ感と蓮根のホクホク感、生姜の辛みと桃の甘みが豆腐に包まれた味わいになりました。
今回の白和えレシピは、「えごま油」を使って混ぜ合わせ、「えごま粉末」を上からかけて仕上げとしました。えごまは「おなかを温めて腸に潤いを補い、上がった気を降ろして咳を鎮める」働きが期待できます。寒さが身体に忍び寄ってきている涼燥の時季なので、こだわって選択してみました。
スーパーで「旬のおススメ」として安価特売だった「水菜」が話のはじまりでしたが、食材の性質・効能を紐解いて見ると、この時季におススメになる理由がとてもよく詰まっています。スーパーで見かける“旬のPOP”は、その季節の身体に最適な処方箋…なのかもしれませんね。
秋の身体もケアする、「かじきまぐろの栗、マイタケ、梅酢ソテー」

2つ目も肺・脾の機能を補うレシピとして「かじきまぐろの栗&マイタケ&梅酢ソテー」を紹介します。春を迎える時季の鮮魚コーナーでかじきまぐろを見かけていたのですが、秋のこの時季にも“旬”として目にすることが出来ました。ついつい嬉しくなって、秋の味覚である栗・マイタケと合せたレシピにしてみました。
作り方は、まず“栗&マイタケ&梅酢タレ”を作ります。栗は水に浸して冷蔵庫で一晩置き、鬼皮・渋皮の順にむきます。鍋に栗が浸るくらいの水と、酒(大さじ2)・みりん(大さじ1)・りんご酢(大さじ1)・白みそ(小さじ1)を加えて15分間煮ます。ここに、縦に割いた後に粗みじん切りにしたマイタケ、種から外して包丁で細かくたたいた梅肉、酒(大さじ2)・みりん(大さじ1)・りんご酢(大さじ1)・白みそ(小さじ1)・水あめ(大さじ1)・水(100ml)を加えてひと煮立ちさせます。
次に“かじきまぐろ”を調理します。かじきまぐろ(切り身2枚)の両面に塩をふって1分置き、表面に出てきた水分をキッチンペーパーに染み込ませて除きます。直後にかじきまぐろの両面に小麦粉(大さじ2)をまぶします。
フライパンにごま油をひいて、かじきまぐろの表面が白くなる程度に火を入れ、“栗&マイタケ&梅酢タレ”を加えて中火で1分程加熱します。器にシソをひいて、盛りつけたら出来上がりです。
かじきまぐろと言うと「春の肝の機能の助っ人」というイメージがあるのですが、鮮魚コーナーで秋にお目にかかれたのには驚きました。熊本県のお隣の鹿児島県では秋の風物詩とも言われているそうです。かじきまぐろは「身体に潤いを補って、気の巡りを助ける」働きが期待できます。気の巡りと言えば肝の機能ですが、呼吸で気の出入りを担う肺の機能にとっても「気の巡り」を助けてくれることは嬉しい働きになります。かじきまぐろは火を入れすぎると硬くなってしまうので、火入れ時間は約1分/片面にすると弾力のある柔らかさが味わえます。
かじきまぐろと合せた栗は「食欲を促して脾の機能を助けて、咳を鎮める」働きが、マイタケは「身体に気を補って、便通を改善する」働きが期待できます。マイタケで“気を補って”かじきまぐろで“気を巡らせる”、ピッタリな相性ですね。
今回はかじきまぐろの色を出来るだけそのまま残して「白い照焼き」にしてみたかったので、しょうゆは使わずに「マイタケの旨味 梅肉」で“煎り酒(いりざけ)”のような味付けをしてみました。ここで砂糖の代わりに使った水あめは「身体に気と潤いを補って、咳を鎮める」働きが期待できますので、一石二~三鳥ですね。涼燥・土用の「寒さが少しずつ増す“変化”の時季」を迎えた身体の助けになれれば幸いです。
“旬を食べる”ということを意識するだけで、肺・大腸・皮膚・毛穴をケアして乾燥に備えることができ、おなかを整えながら脾の機能に働きかけることができます。こうして並べてみると、揃ったな、理論通りだなと感じるとともに、「食材の“旬”は、その時季の身体に摂り込むことがおススメの性質・効能の“目印”」という自然からのメッセージのように感じます。
つづき>>>「旬のものは体にいい」のはなぜ?りんご、さつまいも、柿、秋の旬が体にもたらす「意外すぎる」メリットとは
「田野岡メソッド」のすべてがわかる!1冊の本になりました
「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?
日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。
田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!