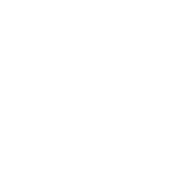レンズ越しに見た「被災地の現実」
社会
ニュース
津波により甚大な被害を受けた宮城県石巻市、南浜町地区。
記者兼撮影担当として同行した私は、取材前「どのように撮れば、被災地の現実が伝わるのか」と考えていた。しかし、その町に一歩足を踏み入れた途端に、その考えがいかに浅はかなものだったかを痛感させられる。
演出的な構図、写真のテクニック…そんなものは、そこでは不要だった。
ただシャッターを押すだけ。それだけで、悲しいほどの「被災地の現実」が切り取られる。
幼い子供が大事にしていたぬいぐるみ。家族のために毎日ご飯を炊いた炊飯器。誰かの大切な足として走り続けたバイク。
その上には、昨夜降った雪が薄く積もっている。
さらに歩みを進め、シャッターを切り続ける。
一階部分を失ったアパートにかかった新規入居者を集う看板。止まったままの時計。
ガラスのない窓にかかる未だカーテンは、その家の奥さんが選んだものだろうか。
津波の後の火事に見舞われた学び舎の中には、焼けずに残った賞状やボールが無造作に落ちている。
人のいない町に、人の暮らした記憶だけが、まだ生々しく跡を残している。
取材や観光目的の人の影はあれど、今「住人」が不在のこの場所は「町」としての命を失っているのだ。
私は、シャッターを切るたびに感じていた違和感の正体に気がついた。
それはまるで亡きがらにカメラをむけているような、底の知れない恐怖感だった。
その後、私たちは場所を移し、「銀だこ」や「銀の鈴」といった店が連ねる「ホット横丁石巻」を訪れた。
被災した方々からインタビューを聞こうと声をかけたものの、「私は被災者じゃないから」と前置きをしてインタビューを拒否された女性がいた。その女性は、こう続けた。「車一台を失くし、買い直したけれど、それだけだから」と。私たちからしてみれば、津波から逃げ、車を失ったという彼女はまぎれもない"被災者"だ。
けれど彼女は「家族や友人を失った人たちもたくさんいる。だから、私は被災者ではない」と言うのだ。
辛く悲しい現実を目の当たりにしてきた彼女の言葉は重かった。しかし、最後に彼女が付け加えた「私には家族も友人もいるから」と言葉が、希望を私に与えてくれた。
この土地に暮らす「人」のすべてを失ったわけではない。
長い年月がかかるかもしれない。解決しなければならない問題もたくさんある。
けれど、再び人が暮らし、この場所が「町」として息を吹き返すことは不可能ではない。
取材を終えた帰路、カメラに収めた写真を見返すと、シャッターを押しながら感じた恐怖は消えていた。
そして、一つの願いが胸をかすめた。
再び目を覚まし、「町」となったあの場所を写真に収めたい。
山と海に恵まれた、美しい町の写真を――。
[文/写真]中村みはる
《NewsCafe》