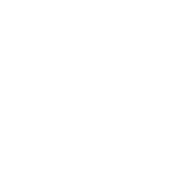この国では虐待は救えないのか
社会
ニュース
公判で下村被告は殺意を否定していました。しかし、西田裁判長は「2人の子どもが相当衰弱して生命の危険性が生じていることを被告も認識していた」などと指摘するなどして、殺意を認定しました。
この事件で問われたのはネグレクト(養育放棄)による虐待死です。虐待には、ほかに身体的虐待、精神的虐待、性的虐待があります。ネグレクトは直接的に危害を加えるわけではありません。むしろ、なにもしないのです。そのため、今回のケースでも、明確な殺意があったわけではなく、食事を与えなければ死亡する可能性が高いと認識しているかが問われることになります。判決はそれを認めたのです。
もちろん、自らの子どもを餓死に至らしめたのですから、殺意がどの程度あったのか、あるいはなかったのかが問題ではありません。いまの日本で親がいるにもかかわらず、餓死という結果になるのは重罪と言えると思います。しかし、どうして防げなかったのか?という視点で議論されていないところに、裁判の限界があるのかもしれません。
この事件では、児童相談所の対応のお粗末さが当初から指摘されています。09年8月、下村被告は名古屋市に住んでいました。このとき長女が愛知県警に一時保護され、中央児童相談所に通告されていました。しかし、下村被告が「生活に困っていることはない」などと言ったこともあり、調査を打ち切っています。
また、10年3月以降、大阪市子ども相談センターに虐待を疑う通報がありました。同センターは何度も下村被告の自宅マンションを訪問しましたが、応答はなかったとして、それ以上の介入はしませんでした。いずれの場合でも、SOSのサインがあり、しかも目の前まで救済の手が届こうとしていたにもかかわらず、児童相談所は介入もできずにいたのです。
この事件の背景としては下村被告が幼いころのネグレクトもあったのです。これは犯罪に直接結びつけることができませんが、下村被告の深層心理や行動パターンを考える上でとても参考になるものです。
下村被告の父親はかつてテレビ番組で取り上げられるほど話題でした。3人の娘を抱えるバツ2のシングルファーザーの高校教師で、不良の巣だったラグビー部を全国大会に出場させ、常連校までに育て上げたのです。しかし、長女の下村被告は暴走族に入り家出を繰り返すのです。
この父親の告白については、『週刊ポスト』でノンフィクションライターの杉山春氏が丁寧な取材をしていますので、バックナンバーで読んでいただきたいと思います。それを読むと、下村被告は性暴力の被害にあい、不登校になりながらも、学校側がきちんと対処できずにいたのです。父親もまた学校との関係に苦労していたということがわかります。
下村被告が「子ども」の頃も、「母親」になってからも、様々なSOSを発し続けてきていました。ネグレクトの被害を受けながらも、自らが加害者に転化してしまったかのようです。よく「虐待の連鎖」という言葉があります。これは単純に「虐待の被害者は、虐待の加害者になる」ということではありません。「虐待の加害者の生育歴を見ると被害者だった過去がある」という意味で、「虐待の被害者が必ず加害者になる」という意味ではないのです。被害を受けた時に、十分なケアがなされれば、加害者になることを防ぐことがあります。
こうしたことを考えると、懲役30年という重い判決は、下村被告だけでなく、虐待された子どもを救えない児童福祉システムへの有罪判決だったのではないかと思えてくるのです。
「この国では、虐待は救えない」。
そんなメッセージが込められているかのような判決でした。虐待から救われるためにはどうすればよいのでしょうか。もちろん、私達が隣近所の住民としてできることもあります。それはこの事件でも、ある程度は機能していたと思います。しかし、救済されるシステムがなければ、何も変わらない。かえって、新たな加害者を生み出してしまう。そんな気がするのです。
[ライター 渋井哲也/生きづらさを抱える若者、ネットコミュニケーション、自殺問題などを取材 有料メルマガ「悩み、もがき。それでも...」(http://magazine.livedoor.com/magazine/21)を配信中]
《NewsCafeコラム》