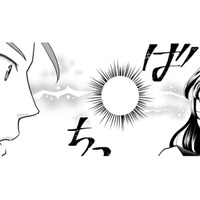ストーカー事件では「被害者の安全確保」が第一。
社会
ニュース
識者は『とにかく突発的・奇妙な事件が多すぎる。「単純に犯人が悪い」だけではかたずけられない不気味さを感じる。明らかに「社会の規範が壊れ始めている」ように思える。一部の学者が「食品添加物の脳への悪影響があるのではないか」と言うのもうなずける』と言う。そんな深刻な話はさておき「今回のストーカーによる殺人事件」はまさに「現代のコミユニケーションの危うさ・警察の仕事の限界」を感じさせるものであった。事の起こりは「フェイスブックによる男女交際」である。
社会学者は『バーチャルの中での「恋愛感情」がリアルになった時「話が違う」はありがちのケースである。普通では「それではサヨウナラ」なのだろうが「男性の女性化現象」の昨今では「男がストーカーになる確率」は高い。今回の犯罪にはフェイスブック以外に「LINEでの殺人の中継的やり取り・ユーチューブの動画を使った彼女自慢・ツィツターでの脅迫的アプローチ」などネットが核となっている。学者が指摘する『ネットにのめりこんだ「ネット脳」は事の重大さの判断がつかないのである』がまさに的中した事件と思えるのである。
この事件対応では「警察の他人事対応」が厳しく指摘されている。確かに警察の「連絡の不手際・連携の悪さ・マニユアル的で臨機応変や洞察力のない対応」には責められるべき点は多い。今月には「警察の連携の悪さ・内部での情報の共有のなさ・危機感のなさ」からついには殺人になったストーカー事件をうけた「改正ストーカー規制法」が施行されたが、それでも対応できなかったのである。警察の仕事はストーカー対応だけではない点で「同情すべき点」はあると思うのである。
ストーカー問題に詳しい大学教授は『加害者(ストーカー)に警告することで加害者が逆上し、凶暴化するケースも少なくない。「殺すぞ」と脅されていたならば「被害者の身の安全を守るため自宅に警察官を派遣させるべき」だったのではないか。この種の事件では加害者(ストーカー)と被害者をまず引き離すことが重要である。改正法では被害者は公的施設等で一時保護を受けられることが明記されている。これらの初動がまず必要ではないか』と指摘している。ストーカー事件では「まず被害者の安全を確保」と思うのである。ストーカーにあっている人の家族や友人もこの原則を忘れないで…。
[気になる記事から時代のキーワードを読む/ライター 井上信一郎]
《NewsCafeコラム》