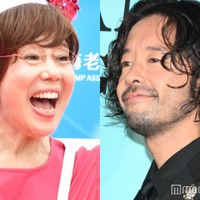「9条」を問うべき安保法制議論
政治
ニュース
そもそも「砂川判決」とは何でしょう。
1955年、米軍立川基地を拡張する反対運動が起きます。いわゆる砂川事件です。57年には農地を強制使用するための測量が行われました。そのときに抗議してた23人が、日米安保条約にもとづく刑事特別法違反の容疑で逮捕されました。このうち7人が起訴されたのです。
東京地裁の伊達秋雄裁判長は「米軍が日本に駐留するのは、我が国の要請と基地の提供、費用の負担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるもの」として、刑事特別法が憲法違反との判決が出されました。いわゆる伊達判決です。
これに対して、日本政府は高裁での審議を飛び越えて、最高裁に上告しました。
最高裁では、原審差し戻しの判決でした。その理由として、安倍政権がよく引用している「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうることは、国家固有の機能の行為として当然のこと」という内容も出てきます。
しかし、これは日米安保条約についての判断であり、基地のための農地の強制使用についての判断です。「(憲法第9条第2項が)禁止した戦力とは、わが国が主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局、わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべき」としています。
つまり、「わが国が主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力」は憲法違反であるが、外国の軍隊の駐留は、憲法違反ではない、という内容です。そして、最終的には「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外」としました。いわゆる統治行為論です。
これは日米安保条約による米軍の駐留は、合憲かどうかは判断せず、ときの政府の判断としたものです。そのため、今回の、自衛隊が海外での武力行為を伴う、集団的自衛権の限定容認を認めているようには読めません。砂川判決の一部の文言だけを引用すれば、安倍政権の解釈にも成り立ちますが、判決の趣旨から考えれば、それは強引だと言わざるを得ないのではないでしょうか。
国会での議論は現在、憲法違反かどうかが中心になっています。ただ、より議論を深めるには、安倍政権がつくりたい安保法制を、誰が見ても「合憲」にするには、憲法改正が必要になります。その意味で、憲法改正が必要か否かを議論する必要があるでしょう。その上で、党議拘束を取りのぞくことができれば、自民党や民主党の枠を超えて、9条維持派と9条改正派とに分かれることになります。
もちろん、安保法制が合憲か否かの議論も必要です。しかし、より本質的には、9条の改正がありかなしかを最終的に議論すべきではないでしょうか。
[ライター 渋井哲也/生きづらさを抱える若者、ネットコミュニケーション、自殺問題などを取材 有料メルマガ「悩み、もがき。それでも...」(http://magazine.livedoor.com/magazine/21)を配信中]
《NewsCafeコラム》