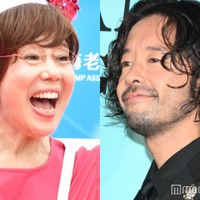今後も沖縄に米軍基地を集中させるべきか
社会
ニュース
辺野古は沖縄本島の中部に位置しています。南部の那覇から行くためには、路線バスで2時間半かかります。高速バスもありますが、途中の宜野座ICまで行き、そこからは路線バスか、タクシーとなります。高速バスで行けば、渋滞を避けることもできますので、時間短縮になりますが、それだけ割高になります。
キャンプ・シュワブ前に、テント村が見えました。この日は私が到着する前に100人ほどが座り込みをしていました。その後も続々と様々な人たちが座り込みに来ていました。反基地運動を長年にわたって取り組んでいる人もいますが、辺野古移転の話が出てから、できるだけテント村に来ているという30代の女性がいました。また「私ができることはなにか?」を考え、月に一回程度は、座り込みに来ているという60代の女性もいました。
ある地域の婦人会の会長はマイクを使って話をしていました。かつて婦人会は、国防婦人会となり、戦争協力をさせられ、夫や子どもを戦場に送っていた一方で、現在の婦人会は反基地運動も担っているというのです。「沖縄県民を馬鹿にするな」と、沖縄の言葉で言っていました。この言葉は、反基地、反米でもありますが、長年沖縄を苦しめてきた本土(大和民族)への怒りの言葉でもあります。
ある参加者が説明してくれました。「これまでは、米軍基地は沖縄県外に移設、という声を上げにくかったんです。それは、基地をどこに移設したところで、基地があることによる苦しみを味わうことになるから。でも、もう沖縄の人たちは我慢の限界を超えつつあるんです。人によってはもう限界を超えています。だから県内移設ではもうダメなんです」。
第二次世界大戦で本土の最終決戦に備え、沖縄が防波堤になり、地上戦が展開されました。沖縄県援護課によると、20万656人が犠牲となりました。うち沖縄出身者は12万2228人。また、その犠牲は、米軍によって殺害されただけでなく、日本軍によっても集団自決に追い込まれ、または殺害されたとも言われています。
さらに、沖縄県が復帰するとともに、米軍基地が残り、戦時中も戦後も、一貫して、本土の捨て駒となってきたとの意識が強くあります。こうした意識について、メディアを通じてなんとなく感じることがありますが、直接話を聞くと、在京メディアで流される声は、相当、トーンが抑えられているように感じます。
さらに言えば、それが「沖縄人=ウチナンチュ」と「本土の人=ヤマトンチュ」との意識差にも現れます。私が「東京から来ました」というと、ある男性は「あなたのことが信用できるできないはわからないが、ヤマトのジャーナリズムは信用できない」と語気を強くして話していました。
「ヤマトのジャーナリズムは、沖縄(基地問題)のことをほとんど取り上げない」とも男性は言っていました。もちろん、本土のメディアも基地問題は取り上げています。しかし、読者や視聴者が「他人事か遠くの出来事かのように受け止めてしまう結果につながるようなスタンスになっている」と言われれば否定できません。こうした沖縄の人の感覚は、震災報道が減ってきたときに、「被災地のことが取り上げられない」と言っていた人たちと似ています。
ヤマトンチュたる私は、沖縄の問題を自分ごとにすることができません。しかし、少しでも沖縄の人々の心情を想像しようと努力することができます。東アジアの軍事バランスも考えなければなりませんが、少なくとも、これまで沖縄に米軍基地を集中させることで、本土の豊かさや平和が保たれてきたことはわかっておきたい。その上で、今後もまた沖縄に米軍基地を押し付けてよいのかを考えなければならないと思いました。
[ライター 渋井哲也/生きづらさを抱える若者、ネットコミュニケーション、自殺問題などを取材 有料メルマガ「悩み、もがき。それでも...」(http://magazine.livedoor.com/magazine/21)を配信中]
《NewsCafeコラム》