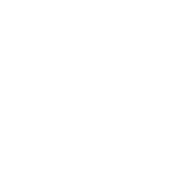こんにちは。神奈川県在住、フリーライターの小林真由美です。ここ数年のマイテーマは「介護」。前回に続き、今回も義母と同時期に経験した「もう一つの介護」について書きたいと思います。その対象となったのは、当時83歳の父です。
日頃から趣味を楽しみ、適度に運動もこなし、地域の活動にも参加。まだ残る黒々とした髪をいつも丁寧に整え、身だしなみには人一倍気を使っている。そんな姿を見ていたからなのか、「介護はまだまだ先」と勝手に思い込んでいた私。でも、そんな父を突然介護することになるなんて。そして、数ヶ月後に「別れの日」が訪れてしまうとは、夢にも思いませんでした。
【アラフィフライターの介護体験記】#10
◀◀前のエピソード がんの末期は「絶望のドラマ」なのか。「家族の日常は消えない」と気付いた日
▶「残念ながらそう長くはない」医師に告げられ、父が「最期」に選んだ場所は
「最期は自宅で過ごされますか?」母と私が出した答え

ありがたいことに、夫の理解や周囲の協力を得て引っ越しをしたことで、私は、ほぼ毎日実家へ行けるようになりました。これまで移動時間を気にしていた父も、「これからは24時間いつでも呼び出せる」などと笑い、私も「バスに乗れば5分だけど、運動のために毎日歩いて“通勤”するよ」と冗談を言っていましたが……。
6月に入ると、父は頻繁に倦怠感を訴えるようになりました。そして、ある朝、血圧が急激に低下していると母から連絡が。すぐに訪問診療医と相談して、胆管ステントの交換が必要な場合も想定し、かつて通った総合病院に入院することが決まりました。
点滴などをして、ひとまず容態は安定。しかし、母と私は主治医に呼ばれ、モニターに映し出された血液検査の結果に目をやると……体に大きな変化が生じていることは一目瞭然でした。
「今までよくがんばりましたね。でも、残念ながら……そう長くはないでしょう。こちらでできる処置をしたら、数日後に退院の手続きをします。最期は自宅で過ごされますか? ホスピス(※1)という選択肢もありますが、急いだほうが良いかもしれません。“間に合わない”可能性もあるので……」
(※1)人生の最期を穏やかに過ごすために、さまざまな苦痛を和らげるための治療・ケアを行う施設。
▶ホスピスで過ごしたかけがえのない日常
「周囲に迷惑をかけたくない」最後まで美学を貫いた父

「間に合わない」と力強い声で伝えた主治医の様子から、あまり時間がないことを確信。母からも、父が昨日「これから先の時間は、病院(自宅ではない場所)で過ごしたい」と言っていたことを告げられました。
「家族を気遣い、迷惑をかけることを嫌う父らしいな」と感じ、それが父の“美学”であることを知っていた私は、「ホスピスに入居したい」と主治医に話します。すると、かつてお世話になった「緩和ケア認定看護師」(※2)が、探してくれることになりました。
(※2)日本看護協会の認定を受け、緩和ケア分野における熟練した看護技術と知識を持つ看護師。 看護師として5年以上の実務経験と、認定看護分野における3年以上の経験が必要。
そしてタイミングよく、私たち家族にとって馴染み深い場所にあるホスピスへ入居できることに! 見学の際、一歩足を踏み入れて感じたのは「家のような温かさがあるな」ということ。さっそく翌日から、父の新しい生活がスタートしました。
私たちは、再びかけがえのない「日常」を手にすることになります。それはまさしく、ホスピスの温かい雰囲気、寄り添ってくれた施設長、看護師や介護士の方々の存在、最後までお世話になった訪問診療医と看護師、ホスピスに繋いでくれた総合病院の主治医、緩和ケア認定看護師、ほかにもあらゆる面で力になってくれた親族や友人がいてくれたからこそ。改めて、感謝の気持ちでいっぱいです。
ホスピスは、24時間家族が同室にいることが可能でした。テレビや小さな家具などの持ち込みも自由だったので、「大谷(翔平)くんが観たい」と言う父のリクエストで、さっそくテレビを設置。自宅で使っていたクッションや小物なども運び、少しずつ部屋作りを進めてゆきました。しかしその途中で、父の容態は急変します。
▶亡くなった今のほうが父を身近に感じている
亡くなった今のほうが父を身近に感じている

その日、明らかに衰弱しながらも意識ははっきりし、会話もできた父。しかし、なぜか母と私は部屋を離れることができず、帰るタイミングを失っていました。
「少し眠るよ」と目を閉じた父に、「また明日来るからね」と言いながら、少し離れた場所で、帰りの交通手段を相談する母と私。「どうしようか。バス? 暑いからタクシー?」などと小声(のつもり)で相談していると、ふいに奥から「今日は暑いから、タクシーで帰ったほうがいいよ」という声が聞こえてきました。
母と私は驚いて再び父の元に行き、「ありがとう。そうするね」と答え、ようやく部屋を出ます。これが亡くなる前日、父と過ごした最期となりました。
あれから1年半ほど経ちますが、不思議と今のほうが父を身近に感じています。毎朝写真に手を合わせて話をするのが日課となり、何か迷いが生じると「父ならどうするかな?」と考える。その存在は、自分の想像をはるかに超えたものになっています。さらに父をよく知る叔母や近所の方と会えば、「昔、こんなことがあってね」と話題が尽きることはありません。
深い悲しみの先には、こんな穏やかな日常が待っていて、そこには今もなお、父がいる。その幸せをかみしめながら、今日も私はもう一つの介護(お義母さん)をマイペースに頑張ろうと思います。