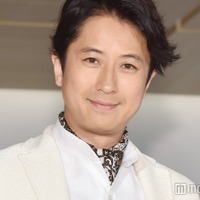日本人女性は平均的に50歳から52歳の間に閉経を迎えます。閉経の前後5年、合計10年を「更年期(周閉経期)」と呼び、女性ホルモン減少に由来してこの時期に起きる不調を「更年期症状」、その症状が耐え難い場合を「更年期障害」と呼びます。
更年期症状がつらい場合、現在日本で選択される主な医療的対策は「ホルモン補充療法(HRT)」「抗うつ剤など非ホルモン薬での療法」「漢方薬」など。第一選択はHRTでしょう。このHRT療法を実施する際に医師が参照する「ホルモン補充療法ガイドライン」が2025年に改訂されました。
私たち患者側が読む機会はなく(とはいえ購入は誰でも可能)、また読む必要も特にはないのですが、どのような点が最新知見として盛り込まれたのでしょうか?
「普通に患者として受診するにはそこまで知らなくてもいいのかもしれない」かなり専門的なHRT知識を、今回のガイドライン改訂に関わった東京大学 大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 産婦人科学講座 准教授 平池修先生に教えていただきます。
先生、質問です。更年期障害が強まりやすい人の「サイン」はあるのでしょうか?
本題に入る前に素朴な疑問です。一般に更年期障害には遺伝性がない、つまり母親が苦しんだからといって娘が苦しむわけではないとされるそうですが、たとえば40代までの間にPMSやそのメンタル版であるPMDDが強かった場合、イライラなどの症状が強まるリスクがある……というような「サイン」はありますか?
「更年期障害を事前に占うことは難しいです。ご質問の件で言えば、まずPMS、PMDDから更年期障害は連動しません」
そもそもPMSもなかなか診断されない傾向にあり、診断がおりると「不調の原因がようやくわかった」と泣いてしまう人もいるくらいなのだそう。
「事前にはわからないとはいえ、同様に更年期障害も診断されて原因が明確になることでHRTを行うなどの対策を立てられますから、喜ぶ人は結構いると思います。このように的確な医療を選べるよう、信頼できるソースの情報提供はいくらやっても足りることはないと感じています」
だからこうした取材もご対応くださるのですね、ありがとうございます。ちなみに平池先生も監修で関与している女性の健康にまつわる情報発信サイトはこちらです。広く全世代の女性が対象ですので、気になることがある人はチェックを。
さて、明確に更年期症状がある場合、HRTは効く人にとてもよく効き、あっという間によくなるので、治療そのものからもあまりドロップしない傾向があるそうですね?
「はい。じつは月経困難症、つまり生理痛などを原因としてピルを飲む人は1年で約半分がドロップすると言われています。何しろ通院も面倒ですし、お金もかかり、毎日確実に飲まねばならないと、途中で止めてしまう理由がたくさん背景にあるのです。一方で、更年期障害のHRTは真逆です。いつまでも続けたいと言う人が多いのが特徴です」
HRTは「実現する快適度」が高い印象がある、と平池先生。ピルの治療は途中でドロップしたという患者さんでも、HRTはあまりドロップしないばかりか、やめたがらない、むしろやめたい人がいないのだそう。メリットのほうが大きいからでしょう、だから我慢せずに治療をスタートしたほうがよいと言います。
ガイドラインに求められる「治療の合意形成」がよりいっそう患者目線に変わりつつある
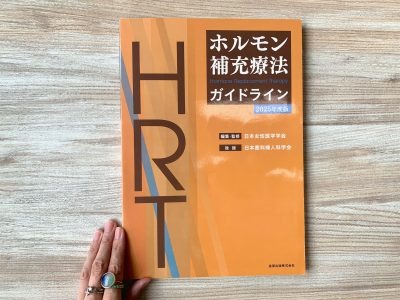
私たちが目にする機会はないものの、医療者の皆さんの多くが参照し指針とするのが「診療ガイドライン」です。通常どの診療領域でも5年ごとに改定され、HRTガイドラインも初版2009年、その後2012年、2017年に改定されましたから、本来ならば2022年に改定のはずでした。
「しかし、この間に『Minds』という、診療ガイドライン自体を評価する公的なシステムが普及しました。途中からMindsに対応するためにこれまでとは根本的に作り方を変えたため、時間がかかりました。従来ガイドライン作成時は医療のエキスパートが集まり、論文をもとに医学的に議論をして策定していましたが、Mindsでは市民の参加も促します。『患者と医療者の双方が科学的根拠に基づいて、合意のうえで最適な診療を選択できる情報を提供する』ことが狙いだそうで、この傾向自体、私たち産婦人科医がそうしようとずっと努力してきた内容ですので、好ましいことだと思います」
Mindsでは合意率も公開され、場合によっては70%を下回る合意率ということもあるのだそう。つまり、3割もの関与者がその内容に合意しなかったという意味です。
「さらに、日本という国の特性も加味されます。たとえば、埼玉県は人口そのものは多いのですが、実は人口比で産婦人科医の数が全国でいちばん少なく、医療アクセス条件がよくない。こうした地域ごとの格差、項目によっては患者さんの経済状況まで考える必要があります」
ほとんどの診療ガイドラインは前半に総論、後半にCQ(クリニカルクエスチョン)が掲載されています。CQとは「現場で医師や患者が直面する具体的な臨床課題」を示す問いのこと。
たとえば今回のHRTガイドラインのCQ402は『60歳以上の女性に対する新規HRTは可能か?』というQです。Aは『明確な適応があり、ベネフィットがリスクを上回る場合に限り可能である』、推奨レベル2、エビデンス3₊、合意率94.1%。
そもそもQ自体も気になる内容ですが、なるほど、Aそのものをどう参考にすべきかの根拠数値も示されているのですね。
「推奨度と質を分けて考え、従来のエビデンスレベルに加えて、推奨レベルのGRADEシステムを導入した点も大きな改訂点です。エビデンスレベルが高くても推奨レベルが弱くなることもあります。このように、薬として有用であることが間違いなくても、リスクと利点を両論併記でお話する、かつ費用面の話もする、じゅうぶんに患者さんにお話ししながら行う治療が現在の主流になりつつあるのです」
ガイドラインには「何が書いてあるのか?」私たちがいちばん気にする「何歳までできるのか」については
2025年版ガイドラインでは、HRTの開始年齢や継続期間についても明確化が図られたのでしょうか? 上記のCQ402は「新規HRT」についてですが、すでにスタートして10年ほど続けてきた現在60歳前後の先輩がたからは「いつまで続けられるのかしら」という不安の声も聞こえてきます。
「閉経前後の50歳近辺から開始して、とても長い期間の投与でなければ、ほぼ問題もないでしょうと考えるのがHRTの主流になるいっぽうで、では80歳前後まで続けるのか?という点には合意が多くはありません。HRTにはリスクもあり、それを説明する必要があるのです」
CQ403「HRTはいつまで継続可能か?」がこの直接的な答えですが、Aは「HRTの継続を制限する一律の年齢や投与期間はない」、推奨レベル1、エビデンスレベル2₊₊、合意率100%。なるほど、エビデンスレベルが最強でなくても推奨レベルは高く、かつ合意率も高い、多くの方がそれが妥当と考えたということですね。今回「一律の年齢はない」とされたものの、「何歳まで」という議論はまだスタートしていないのだと理解しました。
このほか2025年度の「変更点」のうち、オトナサローネ世代に関連の大きいものを編集部が要約すると……
まず、QOL(全死亡率・疲労感・QOL)について、全死亡率を低下させる・疲労感を改善するエビデンスは現時点で存在しないものの、血管運動神経障害、性機能、睡眠に関するQOLが有意に改善している点が記載されました。つまり、HRTでホットフラッシュや睡眠、性機能が改善してQOLが上がることにお墨付きがついたと言えます。
有害事象として新たに肝臓・胆嚢系疾患が記載されました。経口エストロゲンは肝臓での初回通過効果の影響を強く受けるので、肝障害のある患者では肝機能に影響があり、また胆嚢疾患および胆道系手術のリスクが増加します。ただし経皮投与群は経口投与群よりリスクが低いため、貼付剤を使用するなどの工夫が有効です。
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群/閉経に伴うエストロゲン低下によって引き起こされる外陰部・膣・尿路の慢性的な症状や徴候の総称)では、エストロゲン経腟投与は有効と記載されました。ただし全身投与は推奨されず、尿失禁は逆に症状の増大リスクがあります。
反対に、従来、筋組織に対する保護的効果があると推測されていましたが、実はエビデンスが乏しいことが記載されました。ただし運動と併用した場合に筋量・筋力低下を予防できる可能性に言及があります。
乳がんはEP(エストロゲン単独)、EPT(エストロゲン+プロゲステロン)を分けず「施行時は定期的な乳がん検診を行うことが必須である」と明記されました。
静脈血栓塞栓症では経皮エストロゲン投与ではリスクは増加しないと断定的表現になりました。
腰痛に対し、2017年版は有効と書かれていましたが、2025年版はエビデンスなしになりました。
周術期にHRTは中止すべきかについては、一律に中止する必要はないものの静脈血栓塞栓症のリスクに注意することが明記されました。
2017年以来の大きな変化は天然型黄体ホルモン*1の登場です。投与する日数がしっかり決まっているため、投与の数値が記載され、それを受けて投与法の記載が変更されています。相互作用についても変更があります。
ここまでの記事ではHRTガイドライン2025の改訂点をお話いただきました。【関連】記事では「HRTは乳がんを引き起こすのでは?」「子宮筋腫がある人にはNG?」など多くの人が持つ疑問について引き続き詳しい解説を伺います。
関連▶更年期障害の「ホルモン補充療法」に「乳がんになる」と抵抗を感じる人が知っておいてほしい最新情報
編集部注/*1薬剤名称エフメノ
お話/平池修先生
東京大学 大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 産婦人科学講座 准教授。医学博士。1995年東京大学医学部医学科卒業、2002年東京大学 大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学修了。2013年東京大学医学部附属病院講師を経て、2015年より現職。