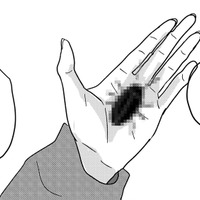「発達障害」を持つ子どもは増えていて、小学校には不思議と
・発達障害の子どもが少なくなるクラス
・たくさんの発達障害の子どもが出てくるクラス
の2種類が存在するそうです。
「『発達障害の子どもを伸ばす大人、ダメにする大人』は明確に存在するのです」
と語るのは、これまで3,000人以上の支援をしてきた発達支援コンサルタント・小嶋悠紀さん。では「発達障害の子どもを伸ばす大人」の、子どもへの声かけや接し方はどのようなものなのでしょう。
今回は、「遊びをやめられない」子どもの「発達障害の特性」と「 遊びへの影響」について、具体例も含めて著書からご紹介します。
※この記事は『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』小嶋悠紀・著(徳間書店)から一部を抜粋、編集してお送りします。
そもそも「発達障害」の特性とは?
発達障害は、主に三つの特性に分かれます。
ASD(自閉スペクトラム症)
集団行動や対人関係の苦手さ、コミュニケーションの苦手さが見られる。こだわりが強く、同じ行動を繰り返すことも多い。感覚が過敏で強く反応しすぎたり、逆に鈍い部分も持ち合わせたりすることも多い。
ADHD(注意欠如・多動症)
注意力、集中力の持続が難しく、衝動的に行動しやすい。小さいときには多動が目立つ。ワーキングメモリの弱さが顕著に目立つ。
LD(学習障害)
知的発達が遅れているわけではないにも関わらず、読み書きや聞く・話す、計算・推論することなど、特定の分野が著しく苦手となる。
これらの特性は、くっきりと分かれて現れるというよりも、一人の子どものなかに混ざり合っており、それがさらに困難さをもたらす場合もあります。家庭生活や学校生活のさまざまな場面に、こうした特性が引き起こす問題が見受けられます。
【次ページ】家庭の遊びはそもそも「区切り」がつけづらい
家庭の遊びはそもそも「区切り」がつけづらい
例えば、家庭には、子どもの大好きなおもちゃやゲーム、動画を見るためのタブレットやテレビなど、遊べるものがあふれています。保護者からの制約がなければ、学校とは違って好きなものに没入できる条件が揃っています。
そのなかでも、ゲームは特に注意が必要です。
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、自分の行動に対して強い報酬を受け取ることに快い刺激を感じます。ゲームでは、自らアクションを起こしてそれが成功すると、必ず何らかの報酬を得られます。発達障害の子どもは特にそこに強い快感を得て、はまりやすいのです。
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、こだわりが強く、自分の好きなものに没入します。今のゲームは、そもそも子どもが没入しやすい仕組みで作られているため、強いこだわりが強化されやすく、やればやるほどゲームに没入していきます。
インターネットを通じて行うオンライン・ゲームなどは、私から見てもまるで沼のようです。そこにいったんはまってしまったら、なかなか抜け出すことができないでしょう。没入感が圧倒的で、途中で簡単に終わりにできない仕組みになっているのです。
そして、ゲームにしても、動画にしても、いったん始めると、区切りをつけることが非常に難しいものです。夕食の支度ができて子どもに声をかけても、ゲームや動画をなかなかやめてくれないといった悩みを抱えている保護者は多いですよね。
学校と違って、家庭は時間割通りに物事が進む場所ではありません。夕食を例に取っても、それぞれの家庭の事情により、日によって時間帯がバラバラだったり、急に外食になったりすることもあるでしょう。子どもにとっては、そうした日常的な変更が、保護者の身勝手に映ってしまうこともあります。
まずは発達障害の特性を理解して、子どもの「納得」を引き出すのがポイント!
遊びの区切りをつけられない子どもと、決められた時間内に遊びをやめさせたい保護者。それぞれに事情があります。では、どのように解決すればよいのでしょうか。
保護者が最初にすべきことは、子どもの特性を理解することです。そのうえで、子どもがしているゲームや見ている動画の内容を、ある程度把握しておくことです。
「○○まで進められたら、手を洗ってごはんを食べようか」などと誘導することで、子どもに区切りをつけさせることができます。
子どもの特性を無視して、こちらのルールを押し付けても、うまくいきません。特に発達障害の子どもの納得を引き出すのは難しくなります。
対立を深めるのではなく、子どもとうまくコミュニケーションを図りながら、ゲームや動画などを上手にコントロールしていくことが大切です。
【次ページ】≪具体例≫「子どもがゲームをやめられない」。あなたはどんな声がけをしますか?
【具体例】「子どもがゲームをやめられない」。あなたはどんな声がけをしますか?
✖ダメにする
「10分後に終わりね!それから夕食だよ!!」と時間で区切らせる
〇伸ばす!
「どこまでやったら終わりで、夕食を始められるのかを教えて」と聞く
家庭では、子どもの遊びを時間で区切ろうとすると、うまくいかないことが多いと思います。学校は、時間割による時間のコントロールに強制力がありますが、家庭では時間的な強制力が弱いので、時間で区切ることが難しいのです。
「あと10分でゲームは終わりね」と言えば、子どもは「わかった!」と気持ちよく返事をしてくれることでしょう。しかし、実際には10分経っても、子どもはゲームのコントローラーを手放しません。
さらに10分が経過し「さっき、10分で終わりにするって言ったじゃないの!」と保護者が怒り出す、毎日同じようなことの繰り返し……。
このようなとき、こちらの都合で時間を区切るのではなく、次のように言ってみてください。
「今、あなたがやっている遊びの区切りはどこでつくの? どこまでやったら終わりにできるの? それを一緒に決めよう。決めたところまできたら、終わりにするんだよ」
と、子どもにとっても納得できる「納得終了ポイント」を、保護者と子どもの両者で相談して決めるのです。
納得終了ポイントがきて、子どもが無事に終了できたら、自主的に終わらせたことを大きく褒めます。するとこれらが徐々に習慣化してきます。子ども本人も、この習慣に慣れてくると、「あー終わった!」と満足して、ご機嫌で夕食のテーブルにやってくるはずです。
【次ページ】≪具体例≫「大事な話なのに、子どもが聞いていない」。話をスルーしがちなのは発達障害の特性。カバーするには?
【具体例】「大事な話なのに、子どもが聞いていない」。話をスルーしがちなのは発達障害の特性。カバーするには?
✖ダメにする
「お耳ついてないの?聞こえてないの?」と責める
〇伸ばす!
「大事な話があるときはチャイムを鳴らす」といった特別な合図を決める
ASDの子どもはこだわりが強く、ゲームなどに熱中していると、保護者が話しかけてもその声が耳に入らないことが多いですよね。
しかも、普段から聞きなれている保護者の呼ぶ声を聞くだけでは、それが「大事なものか」「大事ではないものか」をなかなか判断できないのです。
定型発達の子どもは、保護者の声のトーンから、「あっ、これは今、言うことを聞かないとまずいパターンだな」と判断しますが、発達障害の子どもは、声に潜むトーンの違いを判断することが苦手なのです。
そのため、重要度の高い話があるときには、通常とは異なった方法で働きかけましょう。
例えば、レストランで店員さんを呼ぶ際に鳴らす「チーン!」というチャイム。100円ショップでも売っているこのようなチャイムやベルなどを鳴らして合図にします。
「これが鳴ったら、大事な話があるときだよ」と、子どもには事前に伝えておきます。
もちろん、この方法を使うのは大事な話があるときだけです。1日に1回程度にとどめましょう。1日に何回も使ったら、たちまち効果が薄れます。
「チーン!」と鳴らし、「今日、ゲームはどこまでやってよいか」などを相談します。これを習慣化できれば、成長するうちに、チャイムがなくても「大事な話があるよ」と言うだけで、こちらの言葉を聞いてくれるようになります。
★【関連記事】では発達支援コンサルタント・小嶋悠紀さんが語る、発達障害の子どもが悩みがちな「対人関係」の解決法などを紹介しています。
>>>【関連記事】「発達障害の子ども」の多くが悩む「対人関係」。子どもをダメにする、ついやりがちな「親のしかり方」とは?【発達支援コンサルタントの「効果があった方法」】
■BOOK:『』小嶋悠紀・著
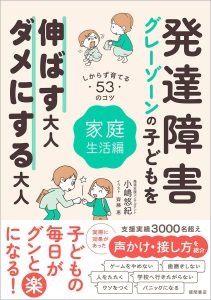
■著者 小嶋悠紀 (こじま・ゆうき)
発達支援コンサルタント、株式会社RIDGE SPECIAL EDUCATION WORKS 代表取締役、特別支援教育総合WEBマガジン「ささエる」編集長。
1982年、長野県生まれ。信州大学教育学部を卒業後、長野県内で小学校の教員を務めながら、特別支援教育の技術などをテーマとする講演を全国で実施。特別支援学級担任・特別支援教育コーディネーターとして、発達理論・科学的知見に基づいた発達支援を10年以上行い、2023年4月より独立。これまで延べ3000人の子どもの支援に関わる。直接的な支援のみならず、教育技術研究所との共同による発達支援製品開発、各都道府県・市町村の教育委員会や生徒へのセミナー・研修・講演会、Web連載、メディア出演などでも活躍。著書に『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ接し方大全』(講談社)『イラストでわかる 特性別 発達障害の子にはこう見えている』(秀和システム)などがある。