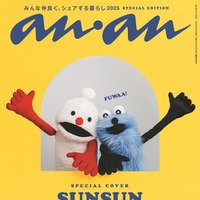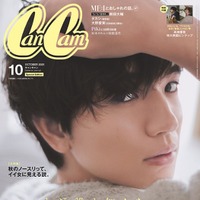*TOP画像/高岳(冨永愛) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」30話(8月10日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「大奥での生き残りをかけた厳しい暮らし」について見ていきましょう。
女子教育の場としての大奥 コネと金を使ってでも娘を大奥に入れたい親たち
大奥女中は他人にお仕えする立場でありますが、生計のために働いている使用人とは動機も心構えも異なるところがあります。将軍のお側で働ける女性は幕臣の娘に限られていましたし、将軍のお側で働く上位の女中にお仕えする女性も商家や裕福な農民の娘がほとんどでした。
裕福な農家や商家の親たちは娘を大奥に入れるため、コネを探したり大金を支払ったりしていました。娘を大奥にそこまでして入れたいと考えるのには理由があります。当時、大奥は花嫁修業の学校、現代でいうと女子校の役割がありました。
大奥は規律や人間関係が厳しいものの、女性としての嗜みや教養を身に着けるには最適な場です。例えば、生け花や茶などの教養、食器の選び方、配膳の仕方、食事のマナー、お辞儀の方法、客のもてなし方、襖の開け閉めなどを仕事を通して学べました。これらは良家に嫁ぐ上で不可欠なものになります。大奥で女性としての嗜みを学び、社会経験を積んだ後、良縁に恵まれた女性は多くいたといわれています。
大奥で働く女性の多くが親から愛情を注がれ、中流以上の経済力の家庭で育ち、大奥女中期間も親から経済的支援を受けていましたが、これから見ていくように、心優しく、おだやかな性格の女性ばかりではありませんでした。
大奥女中生活はワイワイにぎやかであるものの…気疲れしそう
大奥は閉鎖的な空間で、かつ人間関係も複雑であるため、ストレスを感じることは多々あったはずです。現代においても会社への不満ランキングにおいて「人間関係」が1位にランクインすることが多いですが、当時においても人間関係は大奥女中にとって最大の悩みの種だったと思われます。
学校や職場でもいえることですが、大奥での女中生活も仲間が多く、先輩に可愛がられ、変に目立たなければ平穏なものでした。
大奥では身分の上下が厳格であったものの、奥女中は交友関係を楽しんでいました。正月には毬突きや遣羽子で遊んだり、新年のあいさつとして煙草入れやみかんなどを贈り合ったりしていました。また、御年寄や中年寄といった高位の役職者が下の者を部屋に招き、酒や菓子などを振る舞うこともありました。
大奥女中は基本的に相部屋ですので、同じ部屋で暮らす女中と良好な関係を保つ必要があります。円滑な人間関係を維持するための工夫の1つが贈り物でした。例えば、宿下がり(=帰省)の前には、不在中に迷惑をかけることを想定してお金を渡し、帰省後はお土産を渡す慣習がありました。また、実家から贈り物が届くと、同部屋の女中に分け与え、分けてもらった側はお返しをするのが常でした。
他者と関わることが好きな人にとっては余暇や行事は楽しいと思いますが、そうではない人にとっては苦痛だったように思います。いつの時代も、人付き合いが得意で、人の心をつかめる人は穏やかな暮らしを営めるのでしょうね。
女の園では犯罪的ないじめが起きていた。いじめの原因は?
大奥ではいじめというよりも、犯罪に近い行為が多々行われていました。しかも、いじめの原因のほとんどが“嫉妬”です。例えば、第11代将軍・家斎の時代、大奥のあらゆる雑用に従事する御末という役職の女中は、将軍好みの美しい女中を嫉妬心からいじめていたそうです。学校や職場にも一方的に危害を加えて来る人がいますが、被害者にしてみたらたまったものではありません。
さらに、大奥には新人の女中に女性陣の前で裸踊りをさせる、新参舞という行事がありました。新人の中に刺青をしている者がいないか確認するための行事でしたが、大奥女中たちのストレス発散のための行事にいつからか変わったようです。正月の夜、盛大な盛り上がりを見せたらしい…。
本編では、大奥という閉ざされた世界での人間関係の厳しさや嫉妬にまつわる事件を見てきました。
▶▶「俺の絵を描きてえ」母の呪縛を越え…歌麿(染谷将太)に光をくれた再会と蔦重のすれ違い【NHK大河『べらぼう』第30回】
では、舞台を江戸の出版界に移し、蔦重と歌麿のすれ違い、そして運命を変える出会いを描きます。母の言葉に縛られ描けなくなっていた歌麿に、ある人物が差し伸べた手とは…。
参考資料
川口素生、 清水昇『大奥』新紀元社 2007年
中江克己『江戸城の迷宮 「大奥の謎」を解く』PHP研究所 2006年
畑尚子『雑学3分間ビジュアル図解シリーズ 知らなかった!? 大奥の秘密』 PHP研究所2009年