
こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
秋分の時期にケアしたいのは「肺」、そして「大腸」。なぜこの2つなの?
9月23日から10月7日が秋分の暦期間で、陽が極まる夏至と陰が極まる冬至のちょうど中間の時季です。秋分の日は陰と陽が等しいバランスになる日ですので、これから冬至に向けて少しずつ夜の時間が長くなり、季節が冬に向かいます。
今年も秋らしさの訪れがとても待ち遠しくなるぐらい残暑が暑かったですね。彼岸花が咲くころになっても陽射しは強くて、花弁のぴんと張った細い部分は…まるで日焼けしているかのように少しお疲れ気味の花もありました。まだまだ太陽の陽射しからは強さを感じますが、それでも季節は彼岸花が咲くところまで来たのだなと感じました。
夜空の月が人々を癒す時季とも言われています。暦の上では秋のピーク、月を見ながらゆっくり休息しませんかという時期です。そんな秋に気遣いたい腑は「大腸」です。水分を身体に摂り入れる器官ですね。
秋に活躍するのは肺の機能です。人の身体の中で生命活動を支えている五臓六腑という言葉を聞いたことがあると思います。肺の機能にも「臓」と「腑」に分類される機能があり、臓は「肺」で腑が「大腸」になります。この2つの機能はお互いつながっている・連携していると捉えられるので「表裏(ひょうり)関係」と呼ばれます。
どちらかに何かが起きると、連携する相手の側にも変化が起きる。これは悪い影響だけではなく、良い影響も変化として起きるので、秋に肺の機能をケアするということは、肺のコンディションをケアしても良いですが、大腸のコンディションをケアしても良いことになります。
地味なようでいて意外に活躍している影の存在、それが大腸
では、大腸はそもそもどんな働きをしているのでしょうか? 言うまでもなく、身体に水分を摂り込む働きをします。口から飲んだ水分を身体の中に摂り込むのは、胃ではなく大腸です。外気の乾燥が進んで、肌表面や粘膜など身体から水分が奪われやすくなる時期に入っていきますので、“身体への水分の摂り込み”を気遣う意識を高くしたいですね。乾燥の秋…言い換えると「腸活の秋!」に感じます。
水分を身体に摂り込む器官…大腸。実はおたまじゃくしには大腸の器官がありません。水の中で暮らしているので水分を吸収する器官が不要なのでしょう。これがカエルになって大気中で暮らすことが生じると、水分を吸収する器官を体内に作るようになります。これが大腸です。秋から冬にかけて大気の湿度が低い期間になり、身体から水分が蒸散しやすい時季になります。潤い肌をキープするために、あるいは粘膜を乾燥させないために、身体の内側への水分供給が滞りなく行われるように“大腸”のコンディションにいつも以上の気遣いをしていただきたいです。
では、どうすれば大腸のコンディションは整うのか?大腸には腸内細菌という住人がいますので、腸内細菌の働きを整える、あるいは腸内環境を整えることが大事です。大腸にはビフィズス菌が多く存在しています。ビフィズス菌は空気を苦手とする性質があるので、口から胃を経由して小腸あたりまでの空気が存在するエリアは苦手なのですが、大腸には空気はほとんど存在していないので、ココで活動しています。
ビフィズス菌の活動の原動力になるのは食物繊維です。ビフィズス菌を含めた腸内細菌のエサとなって分解されます。食物繊維はさまざまな食材に含まれていますが、大腸の機能を考えると…穀物・雑穀に含まれている食物繊維をおすすめしています。
なぜなら、大腸は水分を吸収する働きをしますが、大便を作って外に出す働きもします。大便は腸内細菌の死骸のかたまりでもあるのですが、その骨格は「前日の朝食に摂った食物繊維」になります。寝ている間は消化活動をしていない胃にとって、朝から嬉しく感じるのは「柔らかい、温かい」食物繊維。お米や穀物は炊飯すると水分を含むので、胃にとって消化しやすい食材に感じます。
寝起きの胃に優しくてビフィズス菌も嬉しく感じる。そんな理由で、“朝一番の食物繊維は穀物・雑穀”をおすすめしています。
大腸のコンディションが整うと、毎朝を快便で迎えることができるようになります。中医学では「肺と大腸は表裏関係」と考えるので、大腸の状態が良くなると、肺のコンディションも連動して良くなります。秋は特に肺の機能をケアしたい季節なので、「乾燥の秋は“腸活の秋”」は中医学的にも合っていることになります。
切り干し大根+玉ねぎの器で秋の入り口のケアが万全に!

“肺・大腸の機能にうれしい食材”でおススメなのは、大根、小松菜、ごぼう、玉ねぎ、はちみつ、こんにゃく、豚の腸、ちんげんさい、クコなどが挙がります。
これらの“肺・大腸の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「玉ねぎ器の切り干し大根と小松菜の煮物」です。大根を干すと甘味が増す話は以前にしましたが、切り干し大根はまさにそのもの。これを肺・大腸に働きかける食材と煮物にして、肺に働きかける玉ねぎの器に入れてみるレシピにしてみました。
作り方は、まず“玉ねぎの器”を作ります。玉ねぎ(中サイズ3個)の皮をむいて、丸ごと15分間蒸します。その後、横半分に切って中心部をフォークを使って取り去ります。(中心部はみじん切りにしておきます)
次に具材を準備します。切り干し大根(20g)は水でもどし、水を絞ってから食べやすい大きさに切ります。小松菜(1袋)は熱湯で30秒ほど茹でた後、約4cmの長さに切ります。ごぼう(1/3本)は皮を削いだ後、ささがきにします。
フライパンにごま油をひいて、玉ねぎのみじん切り・切り干し大根・小松菜・ごぼうを炒め、ごぼうがしんなりしたら、水(300ml)・鶏ガラ粉末(大さじ1.5)・はちみつ(大さじ2)・みりん(大さじ1)・白みそ(大さじ2)を入れて中火で煮詰めます。煮汁が1/3程度になったら火から下ろし、玉ねぎの器に盛りつけたら出来上がりです。
切り干し大根は「身体に潤いを補い、消化を助けて上がった気を降ろす」働きが期待できます。肺の働きには宣発(せんぱつ:身体の上や外に向いた作用)と粛降(しゅくこう:身体の下に向けて散布する作用)がありますが、上がった気を降ろす働きは粛降を助けることにもなるので、肺にとって嬉しい食材になります。これに「身体に潤いを補って便通を改善する」働きが期待できる小松菜と、こちらも「便通を改善する」働きが期待できるごぼうを合せました。器に使った玉ねぎは「身体の気のめぐりを促す」働きが期待できます。
肺の宣発・粛降は“気”の流れですので、身体の気のめぐりを促す玉ねぎの働きは、肺にとって願ったり叶ったりの嬉しい働き。煮物の味付けとして砂糖の代わりに使ったはちみつは「肺に潤いを補い、咳を鎮めて便通を改善する」働きが期待できます。「コホンといったら…肺の気が上がっている」でしたよね。粘膜に潤いを与えて咳を鎮める&腸を潤して便通を良くする働きまで加えました。肺・大腸に負担がかかり始める秋を、負担なく過ごしてもらえるように…そんな願いで作ったレシピです。
レシピバリエの出しにくい「豚ホルモン」がなんと、センスのいい煮物に

2つ目も肺・大腸の機能を補うレシピとして「豚ホルモンの白みそ煮」を紹介します。中医学には以臓補臓(いぞうほぞう)という考え方があり、「不調の部分と同じ臓器を食べることによってその部位の働きを助ける」と捉えています。お肉コーナーのホルモンの棚に並んでいる“豚の腸”には肺と表裏関係の大腸への働きかけが期待できるので、白みそで煮込んだレシピにしてみました。
作り方は、こんにゃく(1/2枚)は2cm幅の薄切りに、大根(1/3本)は5mm厚の銀杏切りに、ごぼう(1/2本)は斜め輪切りにします。にんにく(1片)・生姜(1片)は薄切りにします。(生姜の皮は後ほど使います。)長ねぎ(1本)の白い部分を白髪ねぎにして、クコ(10個)は水につけてもどします。ちんげんさい(1株)はたっぷりのお湯で1分ほど茹でます。豚の腸はスーパーで販売されている形態によりますが、熱湯(ちんげんさいを茹でたお湯)で1~2分ほど茹でた後、ザルにあげて流水でしっかりと洗います。再び鍋にお湯を沸かし、ザルにあげた豚の腸・生姜の皮・長ねぎの青い部分を入れて約5分間茹でて、再びザルにあげます。鍋にこんにゃく・大根・ごぼう・にんにく・生姜・豚の腸・水(800ml)・酒(大さじ5)を入れて加熱して煮立て、きび砂糖(大さじ2)・鶏ガラ粉末(小さじ2)・白みそ(大さじ4)を入れて、約20分間煮込みます。器に盛りつけて、上から白髪ねぎ・クコ・ちんげんさいを乗せたら出来上がりです。
先ほど紹介したように、豚の腸は以臓補臓の考え方で「大腸に潤いを補う」働きが期待できます。これに「大腸に潤いを補い、便通を改善する」働きが期待できるこんにゃくと、「身体に潤いを補い、消化を助けて上がった気を降ろす」働きが期待できる大根を合せて煮込みました。
上から乗せたクコは「肺に潤いを補う」働きが期待でき、ちんげんさいは「身体に潤いを補って乾燥を鎮め、便通を改善する」働きが期待できるので、食材のどれもが肺・大腸のコンディションに働きかけてくれるレシピです。
豚の腸の煮込みというと、名古屋で有名な「どて煮」を思い浮かべましたが、「白い季節の秋」なので白みそを使った煮込みレシピにして、クコを上に乗せた杏仁豆腐のような見映えにしてみました。見た目から食欲をそそられて、「乾燥の秋=腸活の秋」に少しでも働きかけられれば幸いと思って作ったレシピです。
じわじわと人気…「田野岡メソッド」は書籍でもご覧いただけます!
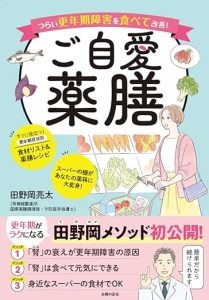
「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?
日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。
田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!








