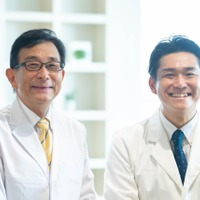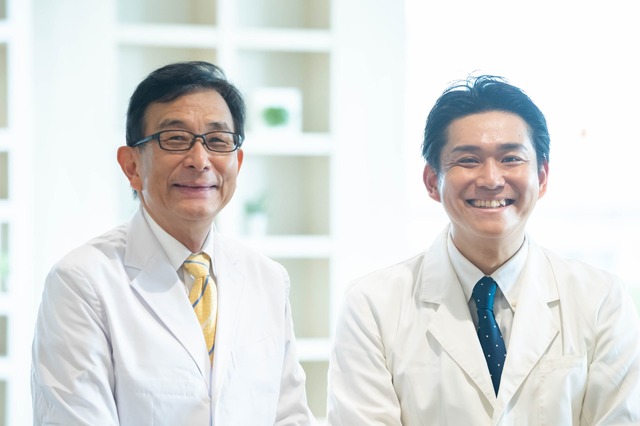
著名人が自身のがん闘病をオープンにするようになり、急激に知られるようになったのが「標準治療」という言葉。国立がん研究センターが提供する情報サイト「がん情報サービス」にはこの「標準治療」について以下のような説明があります。
『なお、医療において、「最先端の治療」が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され推奨されれば、その治療が新たな「標準治療」となります』。
「逆にいえば、先端治療のうち勝率の高いものを標準治療に定めるまでにどうしても『タイムラグ』が発生するという意味でもあります。一刻を争うがん患者にとっては、このタイムラグが極めて重大だということが知られてほしいのです」。
こう語るのは、外科医・免疫学者・漢方専門医のトリプルメジャー医、新見正則先生(新見正則医院 院長)。漢方分野を専門とする薬剤師の笹森有起先生が、がん治療への向き合い方を聞きました。
「冴えた治療」がないのががん治療最大の問題。だから隙間に怪しい医療が跋扈する
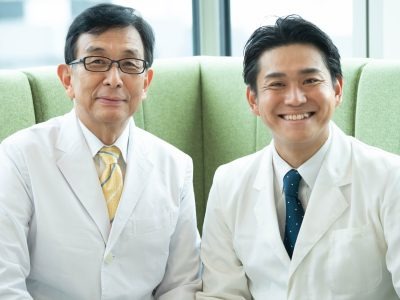
(左から)医師・新見正則先生 薬剤師・笹森有起先生
笹森・標準治療が「最善」の選択肢であることは疑いがないと思います。いっぽう、「最強」ではないという先生のご意見についてお聞かせいただいても?
新見・典型例ががんの生存率です。手術や抗がん剤などの治療後、5年間の継続投薬、経過観察がありますから、どの症例も5年前当時の最善治療の結果なんですね。そこから標準治療にするかのガイドライン議論がありますから、どうしたって10年前の最高の治療なんですよ。ところが現在は医療の進化がとても早く、5年あればどんどん薬も出てくる。
笹森・そうですね、たとえば超高価な分子標的薬なんてどんどん増えていきます。
新見・ぼくは1985年に医師になりました。当時はそれこそ乳がんなんて胸もリンパも根こそぎ取るような大規模な手術一本槍で、抗がん剤も放射線も効くとは思っていなかったので、使用しなかった。
笹森・本当ですか。
新見・はい。でも、手術だけで生存した人がたくさんいらっしゃいます。その後さまざまな治療を組み合わせる方式が確立されて現在に至りますが、手術一本槍からほんのちょっと、治療ごとに10~20%程度生存率が上がった状態でしかない。つまり「冴えたがん治療」がいまだに生まれていないんです。
笹森・「冴えたがん治療」ですか。それはどういう?
新見・たとえば梅毒治療に於けるペニシリンです。早期に発見しさえすれば100%奏功し完治する、だから余計な治療が出てきません。聞いたことないでしょ、梅毒を治すサプリとか。
笹森・梅毒にはペニシリン以外の選択肢を考える必要がないですから、そうですね。
新見・がん治療は、科学者がこうした「冴えた治療」を編み出せていないから不安が残る状態です。不安を埋めたいからよくわからない治療が雨後の竹の子のように登場するのです。冴えた治療の発見に至らない以上は、そうした「その他の治療」、いわゆる「代替治療」「補完療法」だって批判する意味がないとぼくは思っています。ワクチンだって冴えないから反対者が出るんですよ、100%奏功する天然痘のワクチンに文句を言う人は誰もいないでしょう。
笹森・なるほど、奏功しないかもしれない不安は特に説明されずそのまま置き去りにされる、ならば奏功の確率を上げるかもしれない補完療法を否定する必要はないのではという考えですね。
新見・奏功するであろう抗がん剤にしても魔法の杖ではなく、本来ならばエビデンスに限りがあることを明確に説明しないとならない。通常は、臨床試験は、元気でお年寄りではない人が選ばれるのです。その結果から推測して元気がない人や高齢者にも使用しています。元気がない患者さんで一定以上の高齢患者には効く証明がないにもかかわらず、いまはそうした患者さんにも山ほど使っていますよね。
笹森・そうですね、必ずしも使用例がすべてプロトコルに則っているわけではないだろうとは推測します。
新見・美味しいラーメンを食べるとき、チャーシューも煮卵も載せるでしょう、自己判断で載せるトッピングをいちいち否定しなくていい。トッピングが自費診療部分みたいなものです。
笹森・ですが、がん治療時に「何が効いているかがわからなくなるから余計なものを足さないで」と言われるそうです。これはよく耳にします。
新見・それにも違和感があります。スキがあるのは冴えた治療を編み出せない医療側の責任なのに、なんでトッピングを載せたい人を否定するの。さらに言うと、この5年に新しい補完療法として「がんリハビリ」や「腫瘍運動学」なども研究が相当発展しました。これらは特に保険診療の邪魔もしていませんが、全部まとめてエビデンスが薄いと否定する合理性はないですよね。
いちばん重要なのは「運」…? がん治療40年でたどり着いた驚きの結論、その「納得の理由」

新見・医師になって以来40年にわたって、外科、免疫移植、漢方と、3つの新しい専門領域をゼロから学びなおしながら、どうにかがんに効率的なアプローチができないかを追求してきました。その立場から出した結論は、身もふたもないのですが、医療の中でいちばん大事なのは「運」だということ。
笹森・運。
新見・はい、運です。がんは治療開始から5年存命かどうか、5年生存率をひとつの目安にします。たとえばステージ3の乳がんは、40年前、外科手術しかなかった時代でも4割は5年生存しました。ですが今でも、手を尽くしても3割ほどの方は残念なことになる。これを左右するのは何なのか。もちろん患者ご本人には何一つ原因はなく、「冴えた治療」がないことを除けば医療者にも何の手落ちもない。では残りの要素を何と呼ぶか。40年ずっと考えてきましたが、運としか言いようがないのではと。
笹森・ですが先生、医療者の必死の治療、患者の努力、患者家族の祈りを「運」で片づけられるのは……
新見・この運というのは無責任な、ぼーっと座って偶然を待つ運ではない。おっしゃる通り、研究者は全力で研究し、医療者は必死に治療し、患者さんも治るための努力をし、患者ご家族やご同僚、ご友人らはそれを全力でサポートしている。医療とはある意味、「運のかさ上げ」とも言えます。
笹森・なるほど、より運をよくするため、科学的に積み上げていくのが医療という意味でしたら、少し納得します。
がんの生存は「運」であると言い切った新見先生。ここまでの記事ではその前提段階を伺いました。【関連】記事ではLUCKというよりはFATEと言うべき運命の具体的な展開と、FATEを向上すべく医療を選んでいく視座について伺います。
つづき>>「効かないことの証明」はできない。冴えない治療しかない以上は「確率を上げていく」ことが重要ではないのか

■新見正則医院 院長 新見正則先生
新見正則医院 院長。1985年慶應義塾大学医学部卒業。1998年移植免疫学にて英国オックスフォード大学医学博士取得(Doctor of Philosophy)。2002年より帝京大学医学部博士課程指導教授(外科学、移植免疫学、東洋医学)。2013年イグノーベル医学賞受賞(脳と免疫)。20代は外科医、30代は免疫学者、40代は漢方医として研鑽を積む。『フローチャート整形外科漢方薬』はAmazonで三冠(東洋医学、整形外科、臨床外科)獲得。

■薬剤師 笹森有起先生
薬剤師、漢方薬・生薬認定薬剤師。日本薬科大学「漢方アロマ:漢方医療従事者専攻コース」非常勤講師。看護管理者・看護教育者のための専門誌『看護展望』にて「漢方で癒されよう」を連載中。