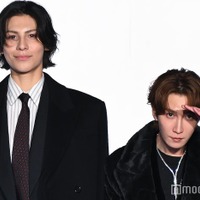*TOP画像/蔦重(横浜流星) てい(橋本愛) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」42話(11月2日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「妊娠出産」について見ていきましょう。
出産は激痛をともなうだけでなく、母子の命にかかわる
当時の出産は座った姿勢で行うのが一般的で、力むときは天井から下がった力綱を握っていました。
ちなみに、“お産のとき藍の実を子宮に塗れば難産にならない”といわれていましたが、現代において科学的根拠はないといわれています。
出産をケガレとみなす風習があり、裕福な家では産室という別室で出産を行い、他の家族から距離を置いていました。こうした部屋がない家では、妊娠した女性は納屋などに隔離され、家族と離れて暮らしました。
江戸時代、生理中の女性はケガレとみなされ、家族と距離を置くために納屋や生理小屋などで過ごしていましたが、妊娠中の女性も生理中の女性と似たような扱いを受けたのです。
加えて、出産後、母親は7日間座った状態で、起き続けなければなりませんでした。これは、子どもを産んだ後に足を伸ばして寝ると、頭に血がのぼって病気になると信じられていたためです。さらに、母親が眠ってしまうと、“生まれた子どもの魂が魔物に奪われる”と信じる地域もありました。母親が寝ないよう、女性たちは大きな声で話したり、親族らは夜通し交代で見守っていました。
出産は母親の命にかかわる高いリスクがあり、かつ激痛をともなうものであったため、出産のリミットは23歳前後ともいわれていました。それでも、当時の女性は5人程度は産んでいたといわれています。
産婆は出産のサポートだけでなく、赤ん坊の“処分”も役目としていた
江戸時代は避妊方法も十分ではありませんでした。当時、避妊薬として、朔日丸(ついたちがん)がよく知られていました。各月の最初の日、つまり1日に飲めば、その月は妊娠しなくなるといわれていたそう。お手頃価格であったため、多くの女性たちが飲んでいたといわれています。
ちなみに、当時はコンドームがありませんでしたが、遊女は膣に紙を詰めて妊娠を回避していたといわれています。
望まぬ妊娠に悩む女性は中条流と呼ばれる堕胎を専門とする医者のもとを訪れることもありました。中条流は水銀などを用いた堕胎薬を処方し、中絶を行いました。
堕胎は法律で禁じられていたため、堕胎専門医は法に触れる職業でしたが、需要があったことから、幕府も黙認していた節があります。
妊娠中絶が間に合わなかった場合や、堕胎の危険性を考慮して出産に踏み切った場合、生まれてすぐに我が子を殺める親も少なからず存在したといわれています。赤ん坊を殺める役割を主に担ったのは、親から依頼を受けた産婆でした。新生児のための洋服などが部屋に用意されていない場合、その家は赤ん坊の誕生を望んでいないことを意味していました。産婆は生まれてきた赤ん坊をどうするべきか雰囲気で察したといいます。
赤ん坊の殺め方は残酷なもので、生まれてすぐ、臼で引いたり、足で踏んだりすることもありました。赤ん坊の死体は俵に入れて川に流すことが多かったそうです。
赤ん坊が残虐な方法で命を奪われた話を聞くだけで胸が締め付けられるほど悲しいと感じる人も多いと思います。しかし、当時は生まれたばかりの赤ん坊に人権はほとんど認められておらず、親の依頼を受けて殺す者も、それを淡々と仕事として行っていたといいます。
本編では、江戸時代の出産や堕胎の実態についてお伝えしました。
▶▶母「つよ」の死、妻「てい」の妊娠……。命がめぐり、生まれ変わる。蔦重が見つめた“生”と“創作”の交差点とは【NHK大河『べらぼう』第42回】
では、命の連なりを通して描かれた蔦重の「家族」と「創造」の物語をお届けします。
参考資料
河合敦『禁断の江戸史~教科書に載らない江戸の事件簿~』扶桑社、2024年
堀江宏樹『女子のためのお江戸案内~恋とおしゃれと生き方と』廣済堂出版、2014年
水戸計『お江戸はつらいよ』彩図社、2023年