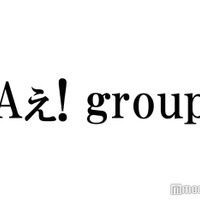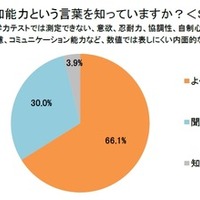ロボットと目で会話…関大が「瞳ディスプレイ」開発
子育て・教育
リセマム/デジタル生活/その他

同研究成果は10月23日と24日に横浜市で開催された「ロボットワールド2025」で発表された。「瞳ディスプレイ」は、人と人が視線を交わすことで無意識に伝え合う「非言語コミュニケーション」をロボットに応用した技術。瞳の中に歩行者の姿を映し出して「あなたを見ています」「認識しています」と伝えるとともに、まぶたを閉じる映像で「速度を落とします」「停止します」と意思表示する。人にとって自然な「目線のやり取り」をテクノロジーで再現し、安全な対話型モビリティの実現を目指している。
この研究は当初、ぬいぐるみ型ロボットへの搭載により「人とロボットが共感し合う視線コミュニケーション」をテーマに進められてきた。そこから発展し、現在は自動運転ロボットやモビリティ機器に焦点をあて、交通環境下での安全対話に研究領域を拡大している。研究室では実物大の横断歩道モデルを設置し、歩行者とのすれ違いや横断時の反応を実験するなど、社会実装に向けた検証が進められている。
瀬島教授は、ロボットに「瞳」を与えることで、単なる機械ではなく「意思を感じられる存在」として人に受け入れられる可能性に注目している。見つめ合うことで生まれる信頼感や安心感は、人間同士の関係に似た心理的効果をもたらすという。こうした「人に寄り添う視線設計」は、将来のスマートモビリティ、医療・介護支援、さらには防犯・防災分野への応用も期待される。
今後は、自動運転車や配送ロボットなどへの実装を見据え、自動車メーカーやモビリティ関連企業との連携を積極的に進める。車両のフロント部やヘッドライト領域に瞳ディスプレイを搭載することで、「ドライバー(またはAI)が歩行者を認識している」ことを明示でき、安全と安心を両立する新しい交通インターフェースが実現するという。瀬島教授は「テクノロジーが人に“目を向ける”時代をつくりたい」と話し、大学発の研究として産業界との共創を呼びかけている。
《風巻塔子》
この記事の写真
/