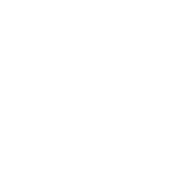日本人の閉経は平均して52歳前後。閉経の前後5年を更年期と呼ぶので、47歳から57歳がこの時期に当たる人も多いでしょう。フェムテック元年の2020年以降、日本でも更年期を取り巻く環境はやや良化したと感じますが、それでもまだまだ情報は取りにくく、助けも得にくいのが現状です。
「これまで、更年期障害は産婦人科医師が一手にその診断と治療を担ってきた分野です。が、私は従来考えられていたよりももう少し『生活習慣の影響を受けるよう』な側面があるのではと考えています」
こう語るのは、オトナサローネではおなじみ、川崎医科大学総合医療センター産婦人科特任部長 太田博明先生。1990年代から現在まで一貫して日本の更年期医療、女性医学の先端に立ち続けてきた太田先生に「日本人女性の更年期、その特徴と解決に向けて」というテーマで5回に分けてお話を伺います。(1/2/3/4/5この記事は5回中の4回目)
何科のクリニックにかかってもある程度更年期症状を診てもらえるのが理想だが
『診療ガイドライン』の存在自体が知られていないこともあり、更年期障害の他科での診療普及については周知に課題があります。他科医師の43%が更年期障害について「あまり関わりたくない」と回答しています。理由は、患者さんの訴えが多様で、診察や検査に時間がかかること、診療報酬を考えると採算が合わないこと、つまり労力と報酬が見合わないことです。
ひとりひとりの診療に時間がかかるわりに、大変な症状がある日、なぜだか原因も解らぬまま、突然よくなってしまってということもしばしばあり、治療の達成感が全くない、治療の手応えがつかみにくい、という点も挙げられます。婦人科との連携も必要だとは思いますが、婦人科では更年期障害は既存の患者さんたちの対応で手いっぱいで、他医からの患者さんを受け入れ診療するゆとりがないというのが実情です。症状の多様性と診断の難しさ、そして診療報酬の問題があります。
『産婦人科診療ガイドライン』2023年版によると、ホルモン補充療法(HRT)はホットフラッシュに対して、推奨度A(強く推奨される)ではなくB(行うよう勧められる)になっています。乳がんのリスクなく行える安全なHRTは対象患者数に限りがあるのではないか、という考え方もある一方で、NAMS(北米閉経学会)からは「65歳以上でHRTを一律に中止にする必要はない」というステートメントも出ています。この点には異論があります。
更年期障害に民族性があるように、HRTの反応についても微妙なところがあり、民族性があるはずです。、日本人女性と他民族の女性との体格差を考えると、本当に同じ薬剤量でよいのだろうかと、思わざるを得ないところもある。それにもかかわらず海外の考え方に追従するばかりで、海外データを吟味した上で、受け入れの可否を決定しているようには思えず、日本独自の考え方やエビデンスをあまり持っていないところに問題があります。乳がんのリスクそのもの自体にも民族差があるはずなのです。
更年期症状の診察に保険加算をつければ「医師も積極的に診察するようになる」かもしれない
かなり大きな問題ですが語られていないのが診療報酬の問題です。更年期障害では、特定疾患療養管理料や、生活習慣病管理料などの指導料や管理料が算定できません。
更年期障害には多様な側面があり、生活習慣病に近いということを学会としてももっと強く訴えていく必要があります。これまで更年期障害を特殊な病気として位置づけ過ぎていたのかもしれません。対象者の80%が何らかの症状を経験するのであれば、もう少しありふれた病気として、把握する方が病状にあっている可能性があります。
ただし、プラセボ効果を認めやすい疾患の特異性があることは事実です。しかし、生活習慣や環境によって発症も考慮されることから考えていくと、「生活習慣病に位置付けられない」と断言されているのは何を根拠にそのように言われているのか……? 学会として十分な我が国の検討もなされていないことは、つまり診療現場で苦慮されている担当医の立場を考慮いただけないことであり、悲しいと言わざるを得ません。
婦人科特定疾患治療管理料は、2020年から器質性月経困難症に対して250点つくようになりました。この婦人科特定疾患治療管理料の枠に、PMSなどと同じように更年期障害も入れるべきだと考えています。生活習慣病(管理料)610点、高血圧660点、糖尿病760点といった水準なのに250点かとも思いますが、産婦人科は全額自費診療の人工妊娠中絶や分娩、一部自費診療の不妊症という特殊な分野があるからか、診療報酬上不遇な面があります。
これはそのまま女性の医療機会の不遇にもつながるのですから、女性のみなさんは産婦人科医と手を携えてもっと声を上げてほしいなと思います。わが国の少子高齢化による人口構成の変化は薬剤の開発や市場性をも考慮せざるを得ない影響をもたらすことが、現場に既に起きてきています。これらのことが医療の現場における過小診断・過小治療に決して結ぶつくことがないことを祈念している。
日本は大病院志向が強く、身の回りのプライマリ・ケア医が育ちにくく、少ないことも課題です。また、未承認薬やオフラベル(適応外使用)ドラッグが増えてきて、ドラッグラグ、新薬承認の遅れどころか、ドラッグロス、国内未導入になっている薬もあります。認知症の薬もアメリカで先に出ました。もはや日本市場を飛ばして直接複数の新興国で作ったほうが早く、経費も安いという経済状況です。人口減少の中では、国内市場だけではやりくりできないというのが現状です。
日本発の新薬「ベオーザ」がホットフラッシュに悩む女性の救世主に!
更年期症状の期待の新薬に、ベオーザ(一般名:フェゾリネタント)があります。ホットフラッシュの緩和が期待できる薬で、日本のアステラス製薬が開発しました。米国ではホットフラッシュを主訴として72%が受診していますが、日本は10.4%に過ぎず、市場が小さいため2023年から先ずは欧米から発売された模様です。
ホルモン補充療法(HRT)は低下したエストロゲンを補充しますが、ベオーザは視床下部に存在する脳内物質のNK3(ニューロキニン3)受容体をブロックし、NK3を低下させるという、エストロゲン作用とは異なる作用機序による画期的な効果の可能性がある薬です。非ホルモン剤ですから、婦人科にこだわらずに内科などでの処方もしやすくなることが期待されます。しかし一方で、HRTとは異なる各種副作用の存在も懸念されていますが、現在のところ米国では5年間に10倍売上高が伸びることが想定しています。なお、因みに肝機能や腎機能への影響と一般的な薬剤の副作用だそうで、内科で対応可能のようです。今後における米国や欧州での有効性と副作用のバランスと普及率が注目されます。なお、日本では2027年の発売が予定されています。
つづき>>>なぜ「更年期のホルモン補充は危険」と誤解されたまま時間がたったのか?
お話/婦人科医・医学博士 太田博明先生
1970年慶應義塾大学医学部卒業。80年米国ラ・ホーヤ癌研究所訪問研究員、91年慶應義塾大学産婦人科講師、95年同大学産婦人科助教授、2000年東京女子医科大学産婦人科および母子総合医療センター主任教授。その後国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授、山王メディカルセンター・女性医療センター長就任し、19年より3年間藤田医科大学病院国際医療センター客員病院教授を兼務、21年より現職の川崎医科大学産婦人科学特任教授、川崎医科大学総合医療センター産婦人科特任部長を務める。日本骨粗鬆症学会元理事長、日本骨代謝学会および日本女性医学学会元理事・監事を務め、日本抗加齢医学会では元理事、前監事を務める。国内の女性医学のパイオニアとして今なお第一線での研究と啓蒙を続ける。1996年日本更年期医学会(現日本女性医学学会)第1回学会賞受賞、2015年日本骨粗鬆症学会学会賞受賞(産婦人科医で初受賞)、2020年日本骨代謝学会学会賞受賞(産婦人科医で初受賞)。著書多数、近著に『若返りの医学 ―何歳からでもできる長寿法』ほか。最新刊はPHP新書『死ぬまで歩ける骨をつくる!本当は怖い「骨卒中」の防ぎ方』。