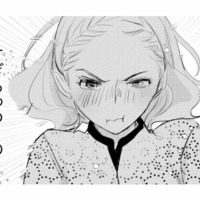【解説】最終回「人格権:生存の権利」
社会
ニュース
判決は『大飯原発を襲う地震の揺れを想定することは出来ない・大飯原発の安全技術と設備は脆弱で住民の安全を確保できない・大事故ほど混乱が大きく思うような収束は出来ない・優先すべきは生存にかかわる人格権で「原発の稼働がコストの低減になる」と言うような「電気代と住民の安全を比較する」のは妥当性がない・安全性を確保できなければ原発を運転すべきではない』と言う明快なものである。識者は『現在大飯原発は3,11後「関西に電気が足りなくなる」と言う理由での臨時稼働を経て「平成13年9月以降は運転を中止・新しい原発規制基準に基ずく原子力規制委員会の再稼働に向けた審査」を受けている。原子力規制委員会は「審査を通る=原発の稼働」ではなく稼働させるかどうかは政治の問題と言っているから「『最後は政治決断』になる。今回の判決は地裁レベルの判決であり確定判決ではないから「政府は再稼働を許可することができる」が現実的には再稼働のハードルは高くなったと思う』と言う。
「安定的・安価な電力の確保」は国民が等しく求める物である。しかし裁判長の「原発の停止で多額の貿易赤字が出ても豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これが失われることが国富の損失である」との判断は「ことのほか重い」と思うのである。畏友は『昔から「法律とは何か」と言う問題提起がある。突き詰めると「法律とは常識の集大成であり、その根底にあるのは市民感覚である」と思う。男性は会社人間になりがちである。主婦の常識が社会の常識に近いのではないか』と言うのである。この問題に関しても「女性の判断」は重要と思うのである。最後に「3年にわたるお付き合い」に感謝してこのコラムを終わりといたします。ありがとうございました。
[気になる記事から時代のキーワードを読む/ライター 井上信一郎]
《NewsCafeコラム》