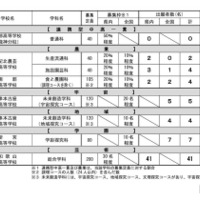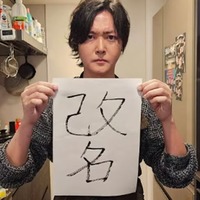小さなころは学習障害で、ご両親をずいぶん悩ませたという、内科医師で小説家の香川宜子氏。勉強に苦労しながらも医師となった後、結婚・出産。生まれた娘さんにも発達障害がありました。香川氏は、今度は母目線で発達障害と向き合うことに。
香川氏の苦労のかいもあり、娘さんは成長してのち、精神科医になりました。母娘ともに発達障害がありながら医師になったふたり。どのような教育が生きたのでしょうか。
【前編】では、香川氏が自らの経験から「6歳までの幼児教育が大切だ」という考えにたどりつき、娘さんが1歳のときから文字を教え始めた様子などをお伝えしました。この【後編】では、その後、自我が芽生えてきた娘さんとどう接し、どんな教育を試みたか、著書『「できんぼ」の大冒険 発達障がい・学習障がいの勉強スイッチ』(徳間書店)から抜粋・編集してご紹介します。
子どもの「やりたい」は、じらして高める!じっと待つこと
時々、うちの子はなにもしたがらないのだが、いったいどうしたらいいか? という親からの質問がくる。そんなものだ。なので親がさせたいものをさせればいいのだ。うちの子はなにをさせても長続きをしないが、どうしたらいいか? そういう親にも以下の答えを用意している。
最も大切な能力の法則がある。
スズキ・メソードに「準・教・育・育」という言葉がある。「準」というのは教材を準備することではない。子どもの意欲が高まるまでじっと待つ。そして心の準備をして教えて育て育てるという意味だ。
私は、あまりやりたいと思わないうちに親にピアノを習わされた。親はピアノを習えば、おとなしくじっとしていられる子になるだろうと思ったらしい。しかし、1年程度でやめてしまった。
スズキ・メソードの教室では、まずは親子で合同レッスン(先生と生徒が一斉に集まって同じ曲を弾く)を見学する。その際、親は自分の子どもを放っておいて、小さなバイオリンを先生から借り、合同レッスンの輪に入って、楽しくバイオリンを弾く真似をする。
子どもは自分と同じくらいの小さな子が、聞き覚えのある『きらきら星』を立派に弾いている中で、身体の大きなお母さんにはふさわしくない小さなバイオリンを持って弾こうとする姿を見る。2歳だったB子は、お母さんにはバイオリンが小さ過ぎて合ってないが、自分ならちょうどいいはずと思うだろう。
この光景を見ていると、2歳の子でも「私もやりたい」とわんわん言うようになる。親はしめしめと思いながらも、その日は連れて帰る。帰る道すがら「あの小さな子、上手に弾いていたね」というと、「私だってできる、やりたいよう」とずっと言う。
そうしたら、「また来週見に行こう」と約束してまた同じようにする。このように「習いたい」と言われても、すぐにその言葉に乗らずに、ちょっとじらすのがポイントだ。
親子の「契約」が、「やめたい」危機を乗り越えるときのカギになる
今度は先生がB子のところへ寄ってきて、箱で作ったバイオリンのおもちゃを持たせてくれる。B子はみんなに混じって同じような仕草で、弓のような棒を上げたり下げたりすると、一斉に『きらきら星』を弾いているので、もう、いっぱしに自分も弾けているように感じる。
先生からは「上手だったね、またみんなと遊びに来てね」と言われる。なんならお菓子をくれたりもする。それでもうB子は有頂天。帰り道で「やりたい。やりたいようお母ちゃん」と半泣きになりながら駄々をこね始める。
そうしたら初めて言う。「途中で嫌になったからやめるとは言わないよね。最後までやると約束できるならしてもいい」と。そこでB子とは、約束するからと言って指切りをする。そうして親子の契約は成立する。
やりたいことだったので、嬉々として練習をするだろう。もちろん週1回は先生が教えるが、あとの6日は先生の代わりに親が教えなければならないので、幼い頃は親がついてのレッスンだ。子どもは親が一緒にいてくれるから、一生懸命にやる。
公文教室も同じ流れだ。2~3歳では線引きから始まる。これは手が疲れないように筆圧の筋肉を鍛えるのだ。子どもより親が先に子どもの前でイチゴからイチゴ、スイカからスイカに線を引いて先生に持って行き、はなまるをもらって先生に褒められて大喜びをしてみる。子どもは絶対に自分もしたいと言い出す。そんなことを数回繰り返してから、本当に行くかどうかを決めればいい。そんな演技を親がするのは正直いってちょっと恥ずかしいが、最初が一番肝心だ。
ところが、やっているうちにB子は飽きてきて、「やめたい」と言い出した。その時に初めて「最後までやめないからバイオリンをさせてほしいって約束げんまん、ママとしたわよね」と聞くと、3歳の子でもうんうんと頷うなずいて納得してまた続けようとする。
このようにB子のやめたい危機は乗り越えていった。ただ、こうした演技のテクニックが使えるのは、小学校1年生頃までだけれど。
子どもの「やりたい」を引き出すのは、親の演技次第!「させられた」感を持たせないのがコツ
「うちの子はなにもしたいとは言い出さない」とおっしゃる親がいるが、幼い頃は親がさせたいものをさせればいい。このような演技力を使わないと、「やりたい」とはなかなか言わないのが当たり前。
メジャーリーガーのイチロー選手や大谷翔平選手も親がさせたいものを親が目的を持ってさせただけで、環境にないものを自らしたいと幼児期に言ったりはしないのだ。
ただ、それには、させた、させられたという感覚を持たさないことが大切なのである。したがって前述した「演技」によって、自らが進んで「やりたい」と言い出すまで待つことが、これから長い人生を渡っていく子どもに非常に役に立つものになっていく。
幼い時から自ら決め、決めたことに責任を持つ。そういう性格構築に役立つのである。
★ここまでの記事では、香川氏が学習障害で苦労した経験をもとに、娘さんの自主的な「やりたい」を育てていく様子をご紹介しました。幼児教育が大切だと考えるようになったきっかけ、どのように幼児教育にとり組み始めたかは【前編】をご覧ください。
★小学校時代、学習障害に苦労をした香川氏自身のお話は【できんぼ母】の記事(#1・#2)をご覧ください。「できんぼ」と先生にあだ名をつけられたこと、自ら「勉強をしよう」と考えるようになったきっかけ、勉強が得意になり医師になる経緯などをご紹介しています。
●BOOK 『
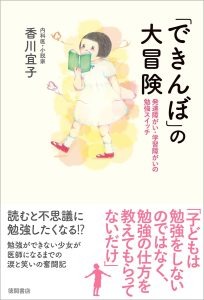
●PROFILE 香川宜子
徳島市生まれ。内科医師、小説家、エグゼクティブコーチ。代表著作の「アヴェ・マリアのヴァイオリン」(KADOKAWA)は、第六〇回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高校の部)、全国インターナショナルスクールさくら金メダル賞受賞。また、「日本からあわストーリーが始まります」(ヒカルランド)は2023年10月にドキュメンタリー映画化。そのほか、「つるぎやまの三賢者」(ヒカルランド)、「牛飼い小僧・周助の決断」(インプレスR&D)などがある。