
こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
秋の土用にケアしてあげたいのは「脾」と「肺」。この2つの関係は?
2025年は10月20日から秋土用に。暦で表現すると、寒露の期間の最後3日間と、霜降の期間を合せた18日間です。秋から冬に季節が移り変わる“変化”の時季ですね。土用ですので、意識してケアしてあげたいのは「脾」の機能です。
秋が深まって乾燥と冷えが同居する“涼燥(りょうそう)”の時季です。肺の機能は、“きれいに澄んだ空気”のような清潔状態を好むので秋に活躍したくなりますが、冷えと乾燥が苦手なので涼燥の時季はケアが必要になります。その涼燥の期間中の土用なので、秋土用は肺と脾の機能を合わせて気遣う意識を持つ必要に迫られる季節です。
肺の機能と言えば、肺・大腸とその影響が顕著にあらわれる皮膚・毛穴・毛。肺の機能は呼吸、宣発(せんぱつ)と粛降(しゅくこう)、毛穴の調整、身体の中に水分を摂取すること…などを役割としていますが、肺はデリケートでもあるので、冷え・乾燥の影響を受けてコンディションが崩れやすくなります。いっぽう、食べたものを身体のパワーに変化させる働きを担う脾の機能は、寒い・冷たいの影響を受けると働きが鈍くなってしまいます。
多くの農作物の実りに恵まれる“収穫の秋”の季節です。農作物の“美味しい旬のちから”を身体に摂り込むためにも、秋土用は“脾”のコンディションを調整したいですね。
脾を補うのは「黄色の食材」。何を食べたらいいですか?まずはちょっと珍しい「なつめ」から

脾の機能を補うのは黄色の食材です。噛むと自然の甘みをほのかに感じられるうるち米(お米)、玄米、きびなどの秋に収穫を迎える穀物、さつまいもなどはおすすめです。そしてもう一つ、天然の食物がもつ優しい甘みで注目したいのが、以前も紹介させていただきました“なつめ”です。また、“脾or肺の機能にうれしい食材”でおススメなのは、ピーマン、豚肉、菊花、クコ、まぐろ、生姜、ねぎなどが挙がります。

これらの“脾or肺の機能にうれしい食材”を使った土用の時季におススメレシピの1つ目は「生ピーマンのなつめ肉詰め」です。脾の機能(=消化機能)に働きかけるなつめ・ピーマン・豚肉で出来るレシピは…と思いながら豚ひき肉を眺めていた時に思いついたレシピです。
作り方は、ピーマン(3個)は洗って縦半分に切り、種を取り除きます。玉ねぎ(中1個)は皮をむいてみじん切りにします。なつめは種を避けて実を外した後、みじん切りにします。クコ(10個)は水につけて戻し、菊花はお湯を沸かしてさっと湯がいて氷水に入れた後、水気を取ります。
フライパンにごま油をひき、玉ねぎの色が変わるまで炒めたら、豚ひき肉(200g)・なつめ・オイスターソース(大さじ1)・しょうゆ(大さじ1)・黒こしょう(小さじ1)・唐辛子(小さじ1/2:お好みで)を加えて炒めます。半分に切ったピーマンに豚ひき肉炒めを盛りつけて、上からクコ・菊花をのせたら出来上がりです。
おススメの食材1番手のなつめは「身体に気と血を補って消化機能を整える」働きが期待できます。季節変化の影響を少なくするかのように、なつめの自然の甘みが身体に気と血を補えてくれる優れものです。このなつめに合わせた豚肉は「身体に気・血と潤いを補って身体の乾燥を鎮める」働きが期待できます。今回、器として活用したピーマンには「身体の中の気の巡りに働きかけて、胃の状態を正常にする」働きが期待できます。気と血を補う働きの食材が重なり、さらに胃の状態を整える働きの食材も加わるので、土用の身体への働きかけの厚みがより増します。上にのせた菊花は「体表の気の流れを良くする」働きが期待でき、クコは「潤いで肺の機能を助ける」働きが期待できます。黄色と赤色の彩り食材でもありますが、この2つの食材のおかげで土用の身体に嬉しい働きかけのあるレシピになりました。
脾or肺にはまぐろ、生姜、長ねぎ。「本まぐろの生姜煮」

2つ目の秋土用におススメのレシピとして「本まぐろの生姜煮」を紹介します。生魚を扱っていらっしゃるスーパーの鮮魚コーナーは“旬”の情報を感じ取りやすいのですが、ふと「本まぐろ」を目にすることがありました。何気なく手に取ってみたのですが…身体がとても欲しているように感じたので、その時にレシピにしてみました。
作り方は、本まぐろ(400g)の冊を4cm角のブロックに切ります。生姜(1片)は皮をむいて薄切りにします。鍋に生姜・酒(大さじ3)・しょうゆ(大さじ2)・きび砂糖(大さじ2)を入れて中火で加熱します。沸騰したら本まぐろを入れて、落し蓋をして中火で5分ほど煮ます。落し蓋を外して、みりんを加えて弱火で5分ほど煮ます。火から下ろして器に盛りつけて、上から長ねぎのみじん切りをのせた出来上がりです。
本まぐろは「身体に気と血と熱を補う」働きが期待できます。一緒に合わせた生姜は「体表の毛穴を開き、肺を温めて咳を鎮める」働き、長ねぎは「体表の毛穴を開いて、食欲を促して消化を助ける」働きが期待できます。身体を動かす源となる気・血・熱を摂り込み、体表を開くことで肺の機能を助け、食欲を促すことで脾の機能を助ける食材の組合せになりました。しかも、まぐろ・生姜・長ねぎは“脾と肺に働きかける温食材”トリオですので、涼燥&秋土用の時季にはピッタリと思い、おススメレシピにしてみました。
おなじみだけど、この季節に急に存在感を増す…「柿」が超優秀!
そしてもうひとつ、干し柿もおすすめです。干し柿の表面の白い粉は「柿霜(しそう)」と呼ばれ、身体の中で水分を生みだす生津(しょうしん・せいしん)と、のどの調子を整える「利咽(りいん)」という効能が期待できます。以前に「コホンといったら」というお話をしましたが、干し柿の白い粉はこの時期の天然の喉のお薬です。干し柿はちょっとお値段が張るかもしれませんが、身体を整えてくれる優秀なお薬…と考えれば、むしろ安く感じたりしますでしょうか。
涼燥で冷えが顕著な日が続いたからでしょうか、山形県に出張に行った際にそこかしこで目にしたのが“干し柿”でした。TOP画像はそのとき撮った写真です。
干し柿は、肺の機能をうるおす「潤肺(じゅんぱい)」と、脾の機能を健やかにする「健脾(けんぴ)」の効能が期待できます。つまり、この時期にケアするべき2つの働きを兼ね備えています。自然は、その時期に必要な効能を“旬”という形で提供してくれます。私たちの暮らしの教科書のようですね。こうした不思議を見つけ出し、触れるたびに、いつも小さく感動します。
柿は生の状態では身体を冷ます性質があります。ですから、秋の入り口のまだ暑さを感じる“温燥(おんそう)”のころには、出回り始めた柿が身体の熱を冷ましてくれます。いっぽう、柿を干すと性質が変わって身体を冷ます働きがなくなります。「柿霜」という天然のブドウ糖を柿の表面にまとって、のどの調子を整えて、身体の中で水分を生みだすことで肺を潤わせます。渋くて食べられなかった柿を甘く食べられるように干すだけでも一つの知恵ですが、身体に優しい状態になって効能も増えると知ると、先人の知恵には感心するばかりです。
暦の上ではそろそろ季節が冬へと移ります。まずは「脾」の機能への意識から冬の準備を始めましょう。次は冬の一歩手前の「霜降(そうこう)」です。
じわじわと人気…「田野岡メソッド」は書籍でもご覧いただけます!
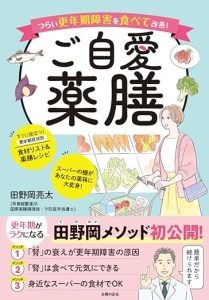
「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?
日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。
田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!








