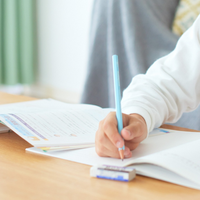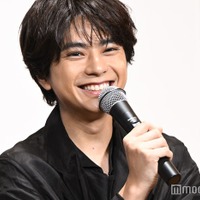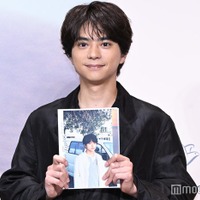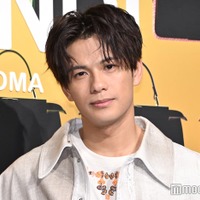2026年度入試のカギは「大阪一強」の行方
--関西における2026年度入試の注目トピックスを教えてください。
2025年度入試を振り返ると、「大阪のひとり勝ち」という印象が非常に強い1年でした。背景には、大阪府の「高校授業料無償化」が想定以上に影響を及ぼしたことがあります。少子化が進む中でも関西圏の受験率自体は高水準を維持していましたが、大阪の受験者数は増加する一方で、周辺エリアは厳しい状況が目立ちました。「周辺地域から大阪市内の学校へ受験する」という流れもあると予想していましたが、むしろ「大阪の中で完結する受験」が目立ち、大阪府内の学校選びが中心となった印象です。
隣県の奈良でも高校授業料無償化における所得制限の撤廃が決まりました。こうした動きにより、2026年度入試では2025年度ほど極端な地域差は出ないかもしれません。ただし、完全に以前の状況に戻るかどうかは不透明で、依然として「大阪一強」の構図が続く可能性もあります。そのあたりが、2026年度入試の大きな注目ポイントですね。
象徴的な例としてあげられるのが、奈良の帝塚山中学校と大阪桐蔭中学校の動きです。帝塚山はもともと女子の進学校として知られ、大阪から電車1本でアクセスできることもあり、長年にわたって大阪の女子受験生に人気の高い学校でした。ところが、2025年度入試では同じエリアにある大阪桐蔭中学校が非常に活況を呈し、帝塚山の志願倍率がやや下がるという現象が見られました。つまり、これまで大阪から奈良方面の学校へと流れていた受験生が、大阪府内の学校で完結する傾向を強めたということです。アクセスの利便性や学校の人気に加え、高校授業料の無償化が追い風となり大阪府内の私学が一段と優位に立った構図です。
いわば「地域間のせめぎ合い」が進む中で、各府県がそれぞれ自県内で受験生を確保しようという流れになっています。
近年の中学受験におけるもうひとつの注目点は、「入試期間の短期化」です。従来、関西では統一解禁日(1月第2または第3土曜日)に多くの学校が入試をスタートし、その約1週間後に大阪教育大学附属池田中学校の入試が行われて幕を閉じるという流れが一般的でした。ところが、附属池田が統一解禁日に日程を移したことで、入試全体が短期間に集中するようになりました。附属池田を併願としてではなく、第一志望とする層の志望動向が全体に大いに関わってくるところです。
「複数回入試」が増え、併願選びにも変化が
 加えて、近年は複数回入試を実施する学校が増えています。しかも、2回目・3回目と受験することで得点が加算されるといった制度を取り入れる学校も目立ちます。これまでは日程が進むにつれて、「第1志望→併願校→安全校」と、偏差値帯や合格可能性を鑑みて受けるスタイルが主流でしたが、同じ学校で「午前・午後の両方を受ける」「今日と明日、別日程で受ける」ことで、「もう1度同じ学校を受けたほうが有利」という選択肢ができました。受験料も優遇されるケースも多く、その結果、これまで別の学校を併願していた層が1校内で完結する受験へとシフトしていく傾向が強まるのではないかと見ています。
加えて、近年は複数回入試を実施する学校が増えています。しかも、2回目・3回目と受験することで得点が加算されるといった制度を取り入れる学校も目立ちます。これまでは日程が進むにつれて、「第1志望→併願校→安全校」と、偏差値帯や合格可能性を鑑みて受けるスタイルが主流でしたが、同じ学校で「午前・午後の両方を受ける」「今日と明日、別日程で受ける」ことで、「もう1度同じ学校を受けたほうが有利」という選択肢ができました。受験料も優遇されるケースも多く、その結果、これまで別の学校を併願していた層が1校内で完結する受験へとシフトしていく傾向が強まるのではないかと見ています。--具体的にどのあたりの学校が複数回入試を導入しているのでしょうか。
代表的なのは関西学院中学部ですね。全国的にも知名度が高い学校ですが、2026年度入試では「A日程」と「B日程」の両方を実施し、A日程を受けた受験生にはB日程で30点を加算するという仕組みを導入します。この「30点加算」はかなり大きく、実質的にA・B両方を受けた生徒が有利になる形です。
こうした制度があると、「まずA日程でチャレンジして、うまくいかなければB日程で再挑戦する」という受験スタイルが定着しやすくなります。その意味では、後半日程に入試を設定している学校にとっては受験者数が減少する懸念もあると思います。
--複数回入試を導入する学校が増えることで、志望度の高い受験生がその学校に集中するということでしょうか。
そうですね。これまでも複数回入試を実施する学校はありましたが、他校との日程の兼ね合いを見ながら受験を組み立てるケースが多かったんです。それが最近では、「この学校に行きたい」という志望度の高い受験生が、同じ学校の複数日程に集中して受けに行く動きが強まっています。背景にはやはり受験期間の短期化があります。以前のように、少し間を置いて別の学校を受ける余裕がなくなり、より短期間で勝負がつくようになってきました。
そのため学校側も、第一志望として考えてくれている受験生や、最初の受験ではうまくいかなかったけれど再チャレンジしたいという生徒を確実に迎え入れる仕組みを整えようとしています。こうした複数日程型・加算型の入試を導入する学校は、関西学院以外にも今後広がっていく可能性があります。
高槻中を中心に人気校の勢力図が変化
--人気校の動向については、どのように見ておられますか。
関東では数年前からすでに見られている傾向ですが、難関上位校の倍率がやや落ち着いてきています。ただし、これは人気が下がったというよりも、いわゆる「併願校」と呼ばれる学校の魅力が高まっていることが大きいと思います。
教育内容の工夫や進路実績の充実など、各校が努力を重ねた結果、受験生や保護者の選択肢が広がっています。コロナ禍を経て学校側も情報発信を積極的に行うようになり、保護者の方も実際に学校を訪れる機会が増えました。偏差値だけで学校を選んでいた時代から、学校の教育方針や雰囲気を重視する時代へと移りつつありますね。
さらに近年は、父親が中学受験に関わるケースも増えています。これまでは母親が「校風」や「雰囲気」などを重視して学校を選ぶ傾向がありましたが、父親はどちらかというと教育内容や学びの中身に注目されることが多い。そうした視点の広がりが、学校選びの基準をより多面的なものにしていると感じます。
--具体的に、人気が集まっている学校にはどのようなところがありますか。
上位層で特に注目されるのは高槻中学校ですね。大阪でも人口が増えている人気の北摂エリアに位置し、今年も多くの受験生を集めると見られています。ただし、近年入学者の学力レベルが上がってきたことで、「受けてみたいけれど、少し難しい」と感じて、特にチャレンジ層は回避する動きも出てきました。
一方で、上位校を目指していた層の可能性を広げる学校が注目を集めています。たとえば、金蘭千里は教育内容の充実や学校改革が奏功し、受験生の関心が高まっています。また、兵庫県の雲雀丘学園も北摂エリアとのアクセスが良いことから、同じように人気を集めています。「教育内容に魅力を感じる学校へ受験生が広がっていく構図」が昨年に続き、今年も続くのではないかと見ています。
--高槻のように人気が上がり、レベルが上がってきた学校はほかにもありますか。
大阪の中でいえば、開明や大阪桐蔭が挙げられますね。大阪桐蔭は、今年から新しい入試日程を設けたこともあって、さらに受験生を集めるのではないかと思います。最近は入試が短期決戦化しており、午前・午後の入試を組み合わせて3日間ほどで一気に受けるという動きが増えています。その中で、高槻や西大和学園などと日程をずらして、うまく併願しやすい形を作っている学校も受験者の増加が目立ちます。
同時に、受験日当日の「移動のしやすさ」も意識されるようになりました。「午前の試験が長引くと午後の学校に間に合わない」という受験生の声に対応して、試験終了時間を早める学校も出てきています。学力や特色だけでなく、日程や試験時間の工夫といった「受けやすさ」も併願校を検討する条件のひとつになっています。
--「受けやすさ」という点では、科目数なども工夫されているのでしょうか。
そうですね。最近は国語と算数に絞るといった形の入試も増えています。関東のように「算数1科目」に絞るケースはまだ多くありませんが、少なくとも午後日程の入試では科目数を減らす、終了時間を早めるといった、受験生・保護者への配慮が見られる学校が増えています。
--今年の出願傾向については、どのように見ていますか。
複数回受験の増加により「出願校数」は絞られますが、「出願回数」自体は例年と大きく変わらないと考えています。1月の統一解禁日の前に、関西以外の学校が大阪や神戸の会場を借りて行う入試を「前受け」として受けるケースが平均1~2校、その後、統一解禁日に本命校を受験するケースが大半だと思いますが、初日の午前・午後、翌日の午前・午後、3日目の午前・午後というように、6校くらいの出願を想定しておいて、実際に受験する学校やコースの数は、想定よりも少し減るケースが多いですね。
「いつものとおり」がいちばんの力になる
 --受験直前期、親に必要な心構えと受験生のメンタルの保ち方についてアドバイスをお願いします。
--受験直前期、親に必要な心構えと受験生のメンタルの保ち方についてアドバイスをお願いします。受験校がある程度決まってきたこの時期からは、保護者は揺れないことが大切です。もちろん保護者自身が不安や迷いを抱くことは自然ですが、それを子供に見せてはいけません。子供は親の気持ちに敏感で、影響を受けやすいからです。
この時期の模試やテストは「合否判定の確認」ではなく、「合格のために何が足りないか」を見つけるためのものと捉えることが重要です。受験生自身も、この段階で目指す学校や点数の基準が明確になっていると、テストや模試の結果の上下に心が大きく揺れなくなります。志望校がはっきりしていると、「無理に高得点を取らなければ」と焦ったり、ミスを恐れて慎重になり過ぎたりということもなく、冷静に実力を発揮することにつながります。
メンタルだけでなく、健康管理も忘れないでほしい時期です。コロナ禍の頃は感染症対策が徹底されていたため、インフルエンザなど他の病気もほとんど流行りませんでした。しかし最近は、コロナへの警戒が緩み、人が多く集まる場所でも以前ほど慎重ではない場合が増えています。その結果、意外なタイミングで風邪をはじめとした感染症にかかるリスクも高まっています。受験直前期は、手洗いやうがい、人混みの過ごし方など、基本的な予防策を改めて意識させることが大切です。心も体も万全な状態で試験に臨めるよう、親として見守りの目を緩めないようにしてください。
--受験当日、子供を送り出す親御さんへのメッセージをお願いします。
受験生にとって大切なのは、「奇跡を起こすこと」ではありません。試験は、普段どおりの力を発揮できるかどうかが勝負です。その日だけ特別に何かができるようになるわけではなく、合格できる力は日頃の努力の積み重ねから生まれます。もしうまくいかないことがあっても、それは「本来できることが試験で出せなかっただけ」ということ。
保護者がすべきことは、子供が普段どおりの状態で試験に臨める環境を整えてあげることです。「親が必死になってしまう」「いつも以上のことを求めすぎる」と、それが子供にとってプレッシャーになってしまいます。冷静ではいられない親御さんの気持ちはわかりますが、できるだけいつもどおりの環境で送り出してあげてほしいと思います。
--ありがとうございました。
秋も深まり、受験生本人はもちろん支える家族にとっても緊張が続く時期を迎える。「特別なことをするよりも、日々のペースを大切にすること」という松本氏のメッセージには、長年の経験に裏打ちされた重みが感じられた。受験生親子のみなさんは、焦らず着実に本番を迎える準備を進めていってほしい。